 |
||
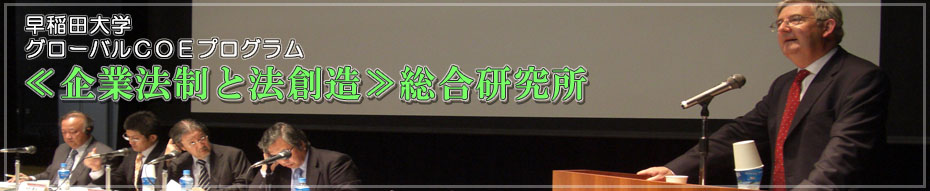
| - �����A | ||
| - �O���[�o��COE�Ƃ� | ||
| - �����̐� | ||
| - �g�D�̐� | ||
| - ���Ɛ��i�S���� | ||
| - �����v���W�F�N�g | ||
| - �����_��(�p��) | ||
| - �G���@��ƂƖ@�n�� | ||
| - �C�x���g���|�[�g | ||
| - ������� | ||
| - �o�ŁE���s���E�_�� | ||
| - ���₢���킹 | ||
| - �j���[�X���^�[ | ||
 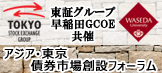 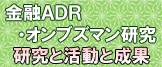 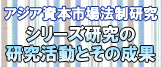  ���ԃv���[������ |
| >>>�Q�P���I�b�n�d�v���O�����̌����v���W�F�N�g�͂����� |
�e�v���W�F�N�g�́u���������v�{�^�����N���b�N���Ē����܂��ƁA�v���W�F�N�g�̋c���^��i���Ȃǂ����m�F�����܂��B
���e�������ɂ͂��ꂼ�ꑽ���̊w���A�w�O���������Q�����Ă��܂��B ���\�\�ȕ���������\����\��ł��B
���e�������ɓo�^����Ă��錤�����́A���ɓ��������҂݂̂Ƃ���Ă�����������A ���ׂĂ̌�����ɎQ�����鎩�R������܂��B �������A�J�Ïꏊ�̓s�����̊W�ŁA�s�\�ȏꍇ�����邽�߁A�������������̌�����ɎQ������ꍇ�ɂ́A ���O�Ɏ����S���҂ɒʒm���Ă��̗�����K�v������܂��B
| �@�����ӔC�� | �@�������S���� |
| �@�̊�b�I�T�O�E�s���Љ�_�� | |
| 1-1.�@��{�I�@�T�O�̃N���e�B�[�N |
| �@���{�̊�ƎЉ�̍\���̉𖾂ɂ́A ���[���b�p���o���Ƃ���ߑ�@�̏��J�e�S���[���A ������{�Љ�ł����Ȃ�ϗe��ւ�Ȃ��痝������p�����Ă���̂��𖾂炩�ɂ���K�v�����낤�B ��{�I�Ȗ@�T�O���`�����ꂽ�v�z�j�I�w�i�ɗ����Ԃ��ĊT�O���ʒu�Â��邱�Ƃ��{�O���[�v�̑��̉ۑ�ł���B �܂��u�@�̑n���v�̉ۑ�Ɋւ��ẮA����t�B�N�V�����Ƃ��č\�����ꂽ�ߑ�@�̏���{�T�O���A �t�B�N�V�����Ƃ��Ă����̈Ӌ`�ƌ��E���l�@�����Ƃ��s���Ƃ����悤�B �u��{�I�@�T�O�̃N���e�B�[�N�v�Ƒ肷��{���������́A ����@�w�Ɗ�b�@�w�Ƃ̐V���������W���\�z���A�V�����@�w�̉\�����J�����Ƃ�����̂ł���B ���̓��e�́A�ꌾ�ŕ\������Ȃ�A��v����@�̈�ɂ������{�I�ȏ��T�O���Ƃ肠���A����explicatio ��Auslegung�i���߁j�A �܂�T���B�j�[���K�肵����̏����̉��ʼn𖾂��邱�Ƃł���B ����͑��ɁA�X�̖@�T�O��@���̔w��ɂ���v�z�A ���̎v�z�����������_�����������Ǝv�������ׂ邱�Ƃł���A ���ɁA���̂悤�ȌX�̖@�T�O�E�@���E�v�z�E���_�����Ȃ���̂��A �ʓI�Ȃ��̂�������������Ƃ�Ƃ���́A�@�̑S�̑��̒��Ɉʒu�Â��邱�ƁA�ł���B |
| ���@����\���@���ѕV�@���\�ʌ� |
| ���@�v�Ĉꐢ |
| 1-2.�@�o�ϖ@�E���یo�ϖ@�̑������� |
| �@�{���́A�O���[�o���[�[�V�����̐i�W�ɔ����Đ�����o�ϖ@�A���یo�ϖ@��̏������������邱�ƂƂ������B���݁A�o�ς̃O���[�o�����ɔ����āA���ۃJ���e���⍑�ۓI��ƌ������s���A���ꂪ���{�s��ɂ��d��ȉe�����y�ڂ��n�߂Ă���B���������ēƐ�֎~�@�̈�O�K�p���߂�����⋣���@�̍��ۓI�Ȏ��s���͂̂�����������ΏۂƂȂ�B�܂�EPA�AFTA�ɂ��Ă��A�P�Ȃ�o�ϓI�����̎��_�����łȂ��A���A�W�A�����̕��a�I�����Ɍ��������͊W�����������ʼnʂ����ׂ��������Ȃ������������邱�Ƃ��d�v�ȉۑ�̈�ƂȂ낤�B |
| ���@�y�c�a���@�{�ԗ��v |
| ���@ |
| 1-3.�@�s���Љ�_�Ɩ@�l�E��� |
|
�@90�N��Ɏn�܂���{�Љ�́u�\�����v�v�́A��Ў�`�A��ƎЉ�Ƃ��ē����Â���ꂽ���{�Љ�̍\�������v�Ώۂɐ�������̂ł������B���������̊Ԃ̍\�����v�ɂ���āA���{�Љ�́A�{���Ɋ�ƎЉ�I�\����E���A���������s�����\������s���Љ�ւƒE�炵���Ƃ����邾�낤���B�{����́A��ƎЉ�Ƃ��Ă̓��{�Љ�̌����_�ł̕ϗe�������ɂƂ炦�邩�A�܂����n�s���Љ�̍\�z�ɖ@�Ɩ@�w���_�͂����Ȃ�������ʂ������邩�A�Ƃ����ۑ�ɁA��b�@�w�I��������A�v���[�`����B��̓I�ɂ́A�i�P�j���{�݂̂Ȃ炸���E�I�ɗ������݂�u�s���Љ�_�v����N����_�_�����A�s���Љ�_�̖@�w�łƂ��Ắu�s���@�_�v���A�s���Љ�`���ɂƂ��ĉʂ�����������ƌ��E�ɂ��čl�@����B�i�Q�j���{�̊�ƎЉ�̂��̊Ԃ̕ϗe�̂���悤���A��Ɩ@�E�J���@�̕���Ƃ��A�g���Ƃ�Ȃ���A�Ƃ�킯�h�C�c�ɂ������Ƃ̕ϗe�Ƃ̔�r��ʂ��Ĕc������B�i�R�j�s���Љ�̒S����̈�Ƃ��đz�肳���A�s���̎����I�A�\�V�G�[�V�������邢�͒n�撆�Ԓc�̂͂̑ΏۂƂ��A���n�s���Љ�ɂ����鋤�����̂���悤��T������B�����ł́u�ߑ�v�Ƃ��̖@���ނ���ے�I�Ɉ����Ă����`���I�c�̂Ƃ����ł̋K�͍\���̍ĕ]�����s���邱�ƂɂȂ낤�B�i�S�j�r�㍑��̐��ڍs�����A���{�Ɠ��������n�s���Љ�̌`�������ʂ̉ۑ�Ƃ��Ď��B���{�͂����̍��X�ɑ���@�����x����W�J���Ă��邪�A����͉ʂ����Ĕ�x�����̎s���Љ�Ɋ�^��������̂Ȃ̂��낤���B����ɂ�����@�̕��Ր��ƁA�����ɂ����铖�Y���̗��j�I�Љ�I�����̊W�A�����ł̖@�̈ʒu�A�@�̈ڐA�\�����߂������_���钆�ŁA���{�Љ�̎s���Љ�ɍۂ��āA���������u�@�v�́A�Љ�\����̗͂���������̂����A���߂čl�������Ă݂����B �@�ȏ��ʂ��āA�t�B�N�V�����Ƃ��Ắu�s���Љ�v�u�s���@�v�Ƃ����J�e�S���[�ɑ�������Љ�ϊv�͂ɁA��̓I�ȃC���[�W��^���邱�Ƃ��A�{�����ǂ̖ړI�ł���B |
| ���@����\���@���q�G�v |
| ���@��v�ۗD�� |
| 1-4.�@�V���I�ɂ������r�@�����̗��_�I�E���H�I�ۑ� |
|
�@���[���b�p�ɂ������r�@�����́A���[�}�@�����Ƃ̐ړ_�̊g���́A��r�@�Ǝ���@�����ߖ@�w�Ƃ̊W���ٖ��ɂ�����悤�Ɏv���邪�A�e���ɂ����郍�[�}�@�p��̍��ق̍\������A���[���b�p�@�`���Ɗe���@�́u�A�C�f���e�B�e�B�v�̊W�����_�I�ɂ����H�I�ɂ��d�v�Ȍ����ۑ�ɂȂ����B���� �ɁA�������𒆐S�Ƃ���EU�Ƃ̊W�Ɍ����Ώۂ�����ׂA���̌����͂���� �Ǝ����𑝂��B���ʁA�䌤�n��50���N�L�O�w�p���f�N�e���̂䂭���x���ۃV�� �|���N���A�ɕ`���o�����悤�ɁA���{����Ƃ������A�W�A�̖@���߂��闧�@ �̓������܂މۑ肪�A��r�@�w�u��i�n��v�̐����Ƃ̊W�ɂ����ċɂ߂ċ� ���ȘA�����`�Â����Ă��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B���̂悤�ɗ��@�Ɖ��߂̃� �x���ŁA�@�I�\���ɂ������r�Ɨ��j�̎��_���A���ĂȂ����x���ō��ۓI �ȋ���������v�����Ă���B�f�|COE�̊�{�R���Z�v�g�́u���n�s���Љ�ɂ��� ���Ɩ@���v�ł��邪�A����͏�L�̓����̒��ł��炽�߂đS�ʓI�ȉۑ�Ƃ���Ă���u�s��v�u�s���Љ�v�u��Ɓv�̏��W�ɂ�����u���O�^�v�̓��o��s���Ƃ��悤�B���̈Ӗ� �ɂ����āA�����A���Ă� ��������r�@�w�̗��_�I�E���H�I�ۑ�ɂ��āA�A�W �A�ɂ��̌��̏���g�債�A���O�̌����҂̋��͂đ����I�Ɍ������邱�� �ɂ���āA��r�@�������̑��݈Ӌ`�������Ƌ��ɁAG-COE�̊���\�z���悤 �Ƃ����̂��A���̃v���W�F�N�g�̎�|�ł���A�ړI�ł���B��̓I�ɂ͎��̂悤�ȍ\���Ńv���W�F�N�g�𐄐i����B �@A�@�����r�@�w�̘_���I�ۑ�i����j�i�䌤�A���u���E���[�N�V���b�v�j �@B�@���ۃV���|�W�E�� �@A�́A��L�̖ړI�ɂ��āA��\�I�ȓ��{ �̌����҂���т��s���̂��C�O�̌����҂����������A���삲�ƁA�����ƁA�n�悲�Ƃ̖��̒T�������݂���̂ł���B��{�I�ɘA���u���̌`���ŕK�v�ɉ����Ĉꕔ��G-COE�Ƃ̋��Ái������Áj�Ő��i�\�Ƃ�������ŁA�䌤�̏���̎葱���J�n����B�C�O�̌����҂ɂ��Ă��Ⴂ���𒆐S�ɂ��s���̂����� ���ɗ��Ă��������u���ƂƂ��ɉ@���Ώۂ̃Z�~�i�[�����肢���邱�Ƃ���������i���̏ꍇ�A��w�@�C�j�V���e�B�u�Ƃ̋�������������j�B�a�́A�`�v���W�F�N�g��i�s�������̒i�K�œ��O�̌����҂����ق���̓I�����I�ȃe�[�}�ŊJ�Â���B�����S�̂ɂ��Ăf�|�b�n�d�̑��̌����`�[���Ƃ��A�g���i�߂�悤�ɓw�͂������B |
| ���@����\���@�����F���@�������Y |
| ���@��v�ۗD�� |
���y�[�W��TOP��
| ��Ƃƌ��@���� | |
| 2-1.�@���@�ƌo�ϒ��� |
|
�@���{�����@�́A�o�ϒ����Ɋւ��閾���K��������Ȃ��B�����Ƃ��A���@29���͍��Y����ۏႵ�Ă���̂ŁA���{��`�o�ς�O��Ƃ�����̂Ɨ�������Ă��Ă͂���B�������A�ЂƂ����Ɏ��{��`�Ƃ����Ă��A�V�ÓT�h�I�Ȏ��R�s�����Ƃ�����̂��畟�����ƓI�Ĕz����g�ݍ��j���[�f�B�[���I�Ȏs��o�ς܂ŁA���̂���悤�͈�l�ł͂Ȃ��B�����Ȃ鎑�{��`��I�����邩�ɂ��āA���@�͖������Ă��Ȃ��̂ł���B �@���̓_�Ɋւ���]���̌��@�w�̑Ή��́A�o�ϒ����̍\�z�𐭍����Ƃ��A�@�I���f�̑Ώۂ��珜�O����Ƃ������̂ł������B����͂������A��d�̊�_�I�v�l�A���Ȃ킿���c��ʂ��Čo�ϒ������\�z����Ƃ����l������O��Ƃ��Ă���B�����ɂ́A�K���������Ƃ̓P�ނ�s��̎��R���C�܂ł𐳓�������Ӑ}�͊܂܂�Ă��Ȃ������B �@�������ɁA���@�͌o�ϒ����̂�����ɂ��Ė��������A�o�ϐ���̓��ۂ͖@�I���f�ɂȂ��݂ɂ����ʂ����B�������Ȃ���A�o�ϒ����́A���̂�����Ɩ��W�ł���킯�ł͂Ȃ��B���̈Ӗ��ŁA���̊�{�\�����߂錛�@���o�ϒ����Ɩ����ł���ƍl����ׂ����R�͂Ȃ��͂��ł���B �@�Ƃ͂����A�O���[�o�������i�W���鍡���̐��E�ł́A�ꍑ�݂̂Ōo�ϒ����̂�������\�z���Ă��A�L�����Ɍ�����ʂ����邱�Ƃ�ے�ł��Ȃ��B�������̐��E�����̍ĕ҂Ƃ����̉��ŁA�������Ƃ̘g�g�݂�O��Ƃ��錛�@�Ȃ�тɌ��@�w���A�o�ϒ����ɂ��Č�蓾�邱�Ƃ͂���̂��B������l���邽�߂ɂ́A�匠��l���A���a��`�Ƃ��������{�����@�̊�{��������̌������s���ƂȂ�ł��낤�B �@�Ⴆ�A���{�����@9���̌f���镽�a��`�́A�o�ϒ����̂������S�����Ȃ��̂��ǂ����B�����ύt�̗v���́A���@��̌����ۏ�Ƃ����Ȃ�W������̂��B����ɂ́A���Ƃ̓P�ނƌ��@�A�Љ�ۏ�ƌo�ϒ����A�n�������ƌo�ϒ����A���邢�͌��@�Ǝs���Љ�X�̖��Ɏ���܂ŁA�{���̎��́A�o�ϓI���R���_��@�l�̐l���_�Ƃ����������̘_�_�ɂƂǂ܂炸�A���l�Ȋg����������̂ł���B |
| ���@�����O�@�������@���V�F |
| ���@�R�{�^�h |
���y�[�W��TOP��
| ��ƂƎs��̖����@ | |
| 3-1.�@�����@�������E�S�� |
|
�@�]�������@�Ƃ�킯���@�͎s���@�^���[���̒���̎g���Ƃ��Ă����B ���Ƃ�肻�̎g���̏d�v���͍���Ƃ��h�����̂ł͂Ȃ��B �����������Ŋ�ƂȂ����s����x����悤�ȏ����I�����@�̂�������^���ɒT������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƂȂ��Ă���B �s��ƕs�@�s�ׁA�s��ɑ���Ӗ��̕s���s�A���Z���i�̐����`���E�K���������A�s����o�R�������ҁE�����Ƒ��Q�̔����A ���Z���i�v�ɌW�閯���@�̈Ӌ`�A�����M���@���A����ҐӔC�A�s�����̋q�̂��郂�m�Ƃ��Ă̌����A ���c�E�@�l�E���Ԗ@�l�E�g���Ƃ��������Ƃ̎M�@�����X�̌����́A��Ƃ��Ė��@�w�҂Ɉς˂��Ă������A �����Ő����Ă��錻�ۂ͊�ƁE�s���S���x���閯���@�Ƃ������_��K�v�Ƃ���ꍇ�������B����Ӗ��ł́A���@�w�҂͂��̌���ŏ��@�w�҂ł������Ƃ��猾����ʂ�����B �{���͂���������������������������邱�Ƃɂ���āA�V���Ȋw��I�n�����J�����Ƃ�����̂ł���B �@�V��Ж@�̐���͏��@�����E���s�ז@�̈ʒu�Â�������Ȃ��̂Ƃ��Ă��邪�A���̕����@�Ɉڊǂ��A��ʎВc�@�l�E���c�@�l����Ж@�Ƃ��Ĉʒu�Â��铙�A���@�Ə��@�̋��E���������A�č\�z����@�^����������B�{���ł́A���������ϓ_����]���̖����@�𑍍�����V�����@���w�̑n����ڎw���B |
| ���@���c�O�@�㑺�B�j |
| ���@ |
| 3-2.�@�����@�̌n�̍č\�z |
|
�@�]�������@�Ƃ�킯���@�͎s���@�^���[���̒���̎g���Ƃ��Ă����B ���Ƃ�肻�̎g���̏d�v���͍���Ƃ��h�����̂ł͂Ȃ��B �����������Ŋ�ƂȂ����s����x����悤�ȏ����I�����@�̂�������^���ɒT������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƂȂ��Ă���B �s��ƕs�@�s�ׁA�s��ɑ���Ӗ��̕s���s�A���Z���i�̐����`���E�K���������A�s����o�R�������ҁE�����Ƒ��Q�̔����A ���Z���i�v�ɌW�閯���@�̈Ӌ`�A�����M���@���A����ҐӔC�A�s�����̋q�̂��郂�m�Ƃ��Ă̌����A ���c�E�@�l�E���Ԗ@�l�E�g���Ƃ��������Ƃ̎M�@�����X�̌����́A��Ƃ��Ė��@�w�҂Ɉς˂��Ă������A �����Ő����Ă��錻�ۂ͊�ƁE�s���S���x���閯���@�Ƃ������_��K�v�Ƃ���ꍇ�������B����Ӗ��ł́A���@�w�҂͂��̌���ŏ��@�w�҂ł������Ƃ��猾����ʂ�����B �{���͂���������������������������邱�Ƃɂ���āA�V���Ȋw��I�n�����J�����Ƃ�����̂ł���B �@�V��Ж@�̐���͏��@�����E���s�ז@�̈ʒu�Â�������Ȃ��̂Ƃ��Ă��邪�A���̕����@�Ɉڊǂ��A��ʎВc�@�l�E���c�@�l����Ж@�Ƃ��Ĉʒu�Â��铙�A���@�Ə��@�̋��E���������A�č\�z����@�^����������B�{���ł́A���������ϓ_����]���̖����@�𑍍�����V�����@���w�̑n����ڎw���B |
| ���@���c�O�@�㑺�B�j |
| ���@ |
| 3-3.�@��ƂƎs��Ɩ����ӔC |
|
�@��Ɗ����ɑ��閯���ӔC�@���A�V���Ȗ�����S�������ɗ��Ă���B�ߔN�i�߂��Ă������O�K���̊ɘa�ɂ���āA����I�Ȓi�K�œ����s�@�s�ז@�̐��ٓI���ʂ��d�v�ɂȂ�ƂƂ��ɁA���O�̋~�ώ�i�ł��鍷�~�����̖��������債�Ă���B�����ł́A�����ӔC�̋@�\���̂̍čl���v�������B�����ɁA���S��������Ȏ�����̊m�ۂ̊ϓ_����A��Ɗ����ɑ���K���ȋK���̂�������A�d�v�Ȍ����ۑ�ƂȂ��Ă���B �@���S�������̌������́A���ׂĂ̎���ɂ����đO��Ƃ����ۑ�ł��邪�A�Ƃ�킯��ƂƏ���҂��Λ�����Ƃ��A���̓���s���̌���I�v���ł���B���S���ɂ́A�����E�g�́E���Y�̈��S�������łȂ��A�����Ȑ�������v���C�o�V�[�̕ی�Ƃ������Ӗ����܂܂��B����̌������ɂ́A��������҂̌����������łȂ��A���������Ɏx����ꂽ���S�Ȏ���s��̊m�ۂƂ������Ӗ����܂܂��B �@��ƂƎs��Ɩ����ӔC�Ƃ����e�[�}���f���Ă��邪�A��Ɗ����ɑ�����@�I�K���̂������A��ƂƏ���҂̊Ԃɂ�����K���Ȏ�����[���A�s�ꃋ�[���̌`���Ƃ������_�̌������A���̃e�[�}���l�@�����ł̕s���ȑO��ł���B�����̉ۑ���܂߂āA�L�����̃e�[�}���������Ƃɂ������B |
| ���@�㓡�����@�Y�쓹���Y |
| ���@���i�q |
| 3-4.�@��ƁE�s���Ɠy�n�@�� |
| �@��Ƃ��s���I��b�Ɋ�Ղ�u�����̂ł���ȏ�A��Ƃ̓y�n�ۗL�ƌl�̐����̂��߂̓y�n�ۗL�̊W���A���ẴP�[�X���Q�l�Ɍ������邱�Ƃ͔��ɏd�v�ł���B�Ƃ�킯�A�R�����Y�Ȃ����Љ�I���ʎ��{�Ǝ��I���L�̊W���l�@���邱�ƂŁA�������Ɠy�n���L�̐����̂�����Ɋւ���Ƃ�킯���B�̔��z���\���ɗ������A�������{�̓y�n����ɐ������Ă������Ƃ��K�v�ł���B�y�n����́A��ƊԁA���L�ςƂ�����b�@�I��Ղ̏�Ɋm�������ׂ��ł��낤�B |
| ���@���c����@�c�R�P�� |
| ���@ |
| 3-5.�@�s��̃O���[�o�����ƒS�ۖ@�� |
|
�@�T�u�v���C����肪�A�����J�̑����Z�@�ւ̓|�Y�������A���E�̎��{�s���h�邪���Ă���B���̖��̏o���_�́A�A�����J�����̌ŗL�̏Z��E�s���Y�S�ې��x�ɂ���B �@����܂ŁA�s���Y�S�ې��x�́A�ꍑ�̌ŗL�̖��Ƃ���Ă����B�������A�u�S�ہv���@�𐧓x���Đ��������Ă����Ղ́u���Z�v���ł��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����āA���Z�u�s��v�Ƃ����̂́A�O���[�o���I������L������̂ł��邱�Ƃ����ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��_�ł���B����̏�L���́A����2�̐��x�̖��ڕs�����ɑ���@�I�z���̌��@���I�悵���Ƃ�������̂ł���B�����ł���A�S�ۂƋ��Z�Ƃ����s�����ɑ���Č����ƁA���Z�s�ꂪ�u�s��v�ł���ȏ�͋���������O��Ƃ��邪�A���̓K���ȋ�������������ׂ��A���{�ɂ��K�Ȏs�ꐭ�K�v�ƂȂ�Ƃ���ł���B �@�����ŁA�����́A���̌o�ϓI�Ȗ����ӎ����A������x�A����̌��_��I�悵�܂��S���E�̃O���[�o���X�^���_�[�h�ɂȂ��Ă��鉢�Ă̋��Z�S�ې��x�����{���猤�����A21���I�̐V���ȋ��Z�̔��W�`�Ԃɑ傢�Ɋ�^���ׂ����x���\�z����K�v�����낤�ƍl���Ă���B�Ƃ�킯�A�A�����J�t�b�b�̔��W�����̖͍��A�d�t����K�͂̔��W�����̖͍��ƎQ���e���̌ʋ��Z����Ƃ̊W�A���ẴA�W�A�s��ւ̃A�v���[�`�̕��@�Ȃǂ́A�K�{�̌����ۑ�ł���B |
| ���@�ߍ]�K�� |
| ���@���T���Y |
| 3-6.�@�M���@���̔�r�@���� |
|
�@�{�����́A�M������ѐM���ގ����x�Ɋւ���@���̔�r�@������ʂ��A�e���̎��@�Ɋւ����{�I�Șg�g�݂̗����Ɖp�Ė@��trust�Ɋւ���Ή����猩���@�ӎ�������W�]�������̂ł���B�܂��A���B�̎��ӁE�Ӌ�������e�I�t�V���A�@��̖@���E�@�ӎ����������邱�ƂŁA�l�X�Ȋp�x����u���[���b�p�v�̐[�w�ɍ����I�ɔ��邱�Ƃ��ŏI�I�ȖړI�Ƃ��Ă���B �@�傽��Ώۂ͈ȉ��̎O�ɕ��ނ����B�@�u���B�𒆐S�Ƃ���嗤�@�����ɂ�����M���ގ����x�ƐM�����̂��̂̎�e�v�A�A�u�X�R�b�g�����h�E��A�t���J�̂悤�Ȃ����鍬���@��(mixed legal system)�ɂ�����M���̎�e�v�A�B�u�I�t�V���A�@��ɂ�����M���@�̓W�J�ƐM���̌��E�A����ђ�G�@�I�ϓ_����̑����ł̃I�t�V���A�M���̎�e�v�B �@���ۓI�W���[�i�����A�p��ɂ�錤�����ʂ̍��۔��M�Ɩ���N��ϋɓI�ɍs���B |
| ���@�n�ӍG�V |
| ���@�،h�V |
| 3-7.�@�q�g�R���������߂���@�I�ۑ� |
|
�@�ߑ�Љ�ɂ����ẮA�����Ƃ��Ẵq�g�͓������o���Ƃ��������݂̂������Č����̎�̂Ƃ��Ĉʒu�Â�����B������̂Ƃ��Ă̐l�́A���l�����������ɏ���������A����̑ΏۂƂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�̂Ƃ��Ă̐l�̐g�̂��番�����ꂽ�g�̂̍\��������A���S�����l�̐g�́i���́j�͐l�i���������A�����̑ΏۂƂȂ肤��Ƃ���Ă������A�����A���̏����̖ړI�Ɠ��e�́A�є��ȂLjꕔ�̂��̂��̂����āA�����̂��߂ł�������A�p���̂��߂ł�������A���邢�͂��������W�{�Ƃ��Ă̂��߂ł������肵���ɂ����Ȃ��B�������A�����A��w�A�����w�A�����Ȋw�ȂǁA���R�Ȋw����ыZ�p�̔��W���A�l�̐g�̂₻�̍\����������Â�n�̑��̏�ʂŗ��p���铹���J���A�����p���▄���̑Ώۂł����Ȃ������g�̍\�������⎀�̂��L����Ӌ`��傫���ω��������B �@���݁A�l�̐g�̂�g�̍\�������͑�ʂ��ĎO�̌`�Ԃŗ��p����Ă��Ă���B���́A�A�����ڐA�ȂǁA�����g�D���̋@�\�����̂܂ܗ��p������̂ł���A���q�◑�q�𗘗p�����o�Y�Ȃǂ����̗ތ^�Ɋ܂܂��B���́A�̎悳�ꂽ�g�̕����������Ƃ��A����ɉ��H�����ė��p������̂ł���B���i��A�ꍇ�ɂ���ĉ��ϕi�Ƃ��Ă����p����Ă��邵�A����Ɍ��ݑ傫���b��ƂȂ��Ă��銲�זE�i���זE�ɂ��Ă��AIPS�ɂ��Ă��j���������A�Đ���Âɖ𗧂Ă悤�Ƃ����̂����̗ތ^�ɑ�����ł��낤�B����ɑ�O�̗ތ^�́A�l��DNA���̎悵�A�������珔��̈�`�I�������o���ė��p���悤�Ƃ�����̂ł���B���̕���́A������q�g�Q�m����͌v�悪�������A�|�X�g�Q�m��������}���Ă�������̎Љ�ɂ����āA����傫�����W����ł��낤�̈�ł���B �@����珔��̕���Ƃ��A���̗��p�̋q�̂̓q�g�i���l�j�ɗR�����镨���ł��邪�A���̗��p�̎��R�x�A�����̉\���Ȃǂɂ��āA�@�I�ɂ���𐳓�������m���ȗ��_�`�����Ȃ���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�g�̍\�������͂����Ȃ錠���̋q�̂��A���L�����A�l�i�����B���̏����͒N������ł���̂��A�܂�����̑ΏۂƂȂ�̂��B���H���ꂽ���i�A���o���ꂽ���Ɋւ��錠���͒N�ɂ���̂��ȂǁA��������Ȃ���Ȃ�Ȃ����_�͑����B�q�g�R�������̗��p�͐l�ނ̕����Ɋ�^����Ƃ��낪�傫���B���̂��Ǝ��̂͋^�����Ȃ����A���Ƃ́A�ߑ�Љ�傫�ȋ]���̏�ɒ͂ݎ���������̎�̂ł���l���̂��̂ɂ��������ł���B�{�����́A�]���̕������_�����ł��A����@�̗��_�����ł��A���邢�͐l�i���̗��_�����ł��Ȃ��A�q�g�R�������Ɋւ���@�I���_�\����T�낤�Ƃ�����̂ł���B |
| ���@��u�a��Y�@�b�㍎�� |
| ���@ |
| 3-8.�@���𒆐S�Ƃ�����Ƃ̖����ӔC�ƌ��@��̐ӔC |
| �@������K�ɉ������邽�߂ɂ́A�����@�エ��ь��@�̗��҂���̑���I�ȃA�v���[�`���d�v�ł���B�{���ł́A�u�i���𒆐S�Ƃ����j��Ƃ̖����ӔC�ƌ��@��̐ӔC�v�Ƃ����e�[�}�̂��ƂŁA�����ӔC�i��ɑi�ׁj�𒌂Ƃ��āA���@��̐ӔC�Ƃ̊W�����܂��Ȃ���A�ȉ��Ɍf����ʂ̖��Ɋւ��i�ׂ���ёi�א��x�̂�����̂ق��A�ӔC�W���p���S�ɂ��Č����E�c�_��i�߂邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B��̓I�ɂ́A��ƂƔr�o�g����A�I�[�t�X���i���c�̑i�ׁj�A�����Q�_�A�y�뉘���̉A�A�X�x�X�g�E��Q�EBSE�E���������߂���i�ׁA�Ȃǂ̘_�_����������B�܂��A���̍ۂɂ́A�������@�̌ʓI�Ș_�_�ɂƂǂ܂炸�A���O���̖@����Ƃ̔�r������ɓ��ꂽ������ڎw���B |
| ���@��˒� |
| ���@�G���q�@�����b |
���y�[�W��TOP��
| ���قƕ������� | |
| 4-1.�@��ƂƎs��ƌY������ |
|
�@�Y���@�O���[�v�́A21���ICOE�̊����̈�Ƃ��āA2004�N�x�ɁA���t�{�o�ώЉ���������̋��͂����āA���{���3,000�Ђ�ΏۂƂ���R���v���C�A���X�E�v���O�����̎��{�y�т��̈ᔽ�s�ׂɑ��鐧�ق̂�����Ɋւ���A���P�[�g���������{���A��1,000�Ђ���̉��B���̒������ʂɊ�Â������V���|�W�E���y�э��ۃV���|�W�E�������{�����i�c����ꁁ�b�㍎��������҉Á����Ό��w��Ɣƍ߂ƃR���v���C�A���X�E�v���O�����x�i2007�N4���A�����@���j�A�b�㍎�����c�����ҁw��Ɗ����ƌY���K���̍��ۓ����x�i2008�N3���A�M�R�Ёj�Q�Ɓj�B���̂悤�Ȍ�������b�Ƃ��āA���{�ɂ������Ƃɑ���Y���K���̂���������������i�b�㍎���ҁw��Ɗ����ƌY���K���x�i2008�N5���A���{�]�_�Ёj�Q�Ɓj�B �@�O���[�o��COE�ɂ����銈�����A�ȏ�̌������X�ɔ��W��������̂ł���A2004�N�x�̍��������ɑ���ǐՒ�����2009�N�x�Ɏ��{����\��ł���ƂƂ��ɁA2009�N�x�ɂ́A���O���ɂ������Ɣƍ߂̌���Ƃ���ɑ���Y�����ق̂�������߂��鍑�ے��������{����\��ł���B�����̌��������{���邽�߂ɁA2008�N�x���猤���̐����������A��������������@�����O���[�v�ƊO���@�����O���[�v�ɕ����A���O���[�v�̌��������s�Ői�߂邱�ƂƂ����B���̂����A���ے����ɂ��ẮA���O���ɂ������Ɣƍ߂ƃR���v���C�A���X�E�v���O�����Ƃ̊W�ɗ��܂炸�A����ɂ��̔w��ɑ��݂����ƕ�����s���ӎ��ɔ��钲�������{�������ƍl���Ă���B�����̏��������͂��ł�2008�N�x����n�܂��Ă���B |
| ���@�c�����@�b�㍎���@�]���ЕF |
| ���@�H�쐳�m�@�Җ{�~�j�@��덹�D�@���R�D�T |
| 4-2.�@��ƂƎs��ƕ������� |
| �@�{���͎�Ƃ��Ė����@�̗��ꂩ���ƂƎs��ƕ����������e�[�}�Ɍ������s�Ȃ��B�����ł́A�Y���@�Ƃ̐ړ_�ł����閯�����فA�ے����A�����I���Q�����Ƃ��������َ�i�͂��Ƃ��A������ADR(�ٔ��O����������i)�̐��i�ƈӋ`�A���邢�͎���K���@�ւɂ��K�����L���錠�ЂƂ����������̖��������ΏۂƂ���B |
| ���@�����N�v�@�Y�쓹���Y |
| ���@ |
���y�[�W��TOP��
| ��ƂƘJ���E�� | |
| 5-1.�@�J���@�ɂ������ƊT�O���߂��錤�� |
| �@�J���@�Ɗ�ƂƂ̊Ԃɂ͖��ڂȊW�����邪�A����܂ł̘J���@���_�́A��Ƃ�J���_��W�̈�������҂Ƃ��Ă����݂邱�Ƃ��Ȃ��A��ƂI�v�f�i�H��E�{�݂Ȃǁj�Ɛl�I�v�f�i����E�o�c�ҁE�J���ҁE���҂Ȃǁj���琬��S�̂��Ă݂邱�Ƃ͂Ȃ������B�Ƃ��낪�A��Ɩ@���̉��v�ɂ���đ��i���ꂽ��Ƒg�D�̕ϓ��́A��Ƃ��̂��̂̉^�����J���҂̖��^�������邱�ƂɂȂ邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B�]���A�@���w�ɂ������ƊT�O�̌����͂����ς珤�@�w�E��Ж@�w�Ɉς˂��Ă������A�����������ŁA�J���@�w���܂��A���J���@�ɂƂ��Ă̊�ƊT�O���̌����̕K�v���ɔ����Ă���B�{�����ɂ����ẮA���@�w�E��Ж@�w�̂���܂ł̌������ʂɊw�сA�����ƑΘb���A�J���@�w�ɂ������ƊT�O�̐ϋɓI�ȍ\�z�����݁A�J���@�̊�b���_�̍Č����ɂ܂Ŏ����ƍl���Ă���B |
| ���@�Γc���@���c�z�� |
| ���@��؏r�� |
| 5-2.�@��Ɣ����E�g�D�ĕ҂ƘJ�� |
| �@�u����v�����݊��𑝂��Ă��鎞��A�����t�@���h�Ȃǂɂ���Ɣ����Ƃ���ɔ����g�D�ĕ҂��J���W�̖@�I�ȑ��ʂɂǂ̂悤�ȉe��������ڂ��̂��́A��Ж@�w�݂̂Ȃ炸�A�J���@�w�̏d�v�Ȍ����ۑ�ł���B��̓I�ɂ́A�]���̘J���@�w���c�_�̑Ώۂɂ��炵�Ȃ������u����v��u��Ɖ��l�v���u�J���v�Ƃ̊֘A�ŋc�_���悤�Ƃ���̂��A�{�����̎�|�ł���B��Ɩ@���̕ϑJ�̒��ŁA�ǂ̂悤�Ȋ���́A�ǂ̂悤�ȍs�����A�u�J���v�̊ϓ_����݂Ăǂ̂悤�Ȗ�����N������̂��𑨂��邱�Ƃ��܂��K�v�ł���A��������̌������A�J���@�w�Ɖ�Ж@�w�̋��������Ƃ��Ď����������ƍl���Ă���B |
| ���@�Γc���@���c�z��@�㑺�B�j |
| ���@��؏r�� |
| 5-3.�@��ƁE�s���Љ�ƐV���ȎЉ�@ |
|
�@���ȗ��̂킪���̐����E�ɉh���x���Ă����o�ρE�Љ�V�X�e�����ǏɊׂ钆�A�K�����v�Ȃǂ̍\�����v�Ɍ��������ƓI��g���Ȃ���Ă����B�����������A�u�i���Љ�̓����v�u�n���̊g��v�Ƃ��������t�ɏے������悤�ɁA���������\�����v�̉��łƂ�����Βu������ɂ��ꂪ���Ȃ�����Љ�I��҂ւ̕s�\���Ȑ����I�Ή��̂�����ɑ��Ă��A�œ_�����Ă�����B �@�{���ł́A�����������{�Љ�̂����ꂽ����ɑ��A�u�Љ�@�v�̎��_������g�ނ��Ƃ��˂炢�Ƃ��Ă���B���A�J���@�w���玟��ɎЉ�ۏ�@�w���������A�w��I�ɂ������҂̑w�Ƃ��Ă��A���ΓI�ɓƗ��������̂����̖@����ł͂��邪�A�K�ٗp�A���[�L���O�v�A�ȂǁA�������J���ƎЉ�ۏ�̗��ʂ��瓝���I�ɃA�v���[�`���邱�Ƃ����߂��鎞��Ɏ������Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B�����ɐV���ȁu�Љ�@�w�v�̍\�z�̕K�v�����F�߂���Ɠ����ɁA���̊�ՂƂȂ�V���ȁu�Љ�v���߂���c�_�̓W�J���傫�Ȋw��I�ۑ�ł���B �@�{���ł́A���������ۑ�ɖ{�i�I�Ɏ��g�ޑO�i�K�Ƃ��āA���N�x�A�@�w�����҈ȊO�̑����̓��{�l�����҂����ւ����A�u�n���̊g��ƃZ�[�t�e�B�l�b�g�̖����`�i���Љ�ɂ�����Љ�@�̍č\�z�`�v�Ƒ肵�āA�V���|�W�E���`���̌������2009�N1��17���i�y�j�ߌ�ɗ\�肵�Ă���B |
| ���@�e�r�]���@��q�ނq �Γc���@���c�z�� |
| ���@��؏r�� |
| 5-4.�@�n�������Ɗ�Ƃ̐ӔC |
|
�@�����̒n�������Ɋւ��ẮA���{�݂̂Ȃ炸���O���ɂ����Ă���Ɗ����Ɋ��z�������߂���悤�ɂȂ��Ă���B�܂����Ɋւ���@���x�͕ω��������A�Ⴆ��EU�ł͐V�����w�߂̐��������̎w�߂̉��������N�������s���Ă���A��Ƃ͂����@���x�̓����ɑΉ�����悤���߂��Ă���B �@�������ɂ����ẮA���E�̖@���x�A�Ƃ�킯EU�E�A�����J�̖@���x���X�̍��ۏ���f�ނƂ��A�����������t����T�O�ƂȂ����u�\�h�����v�A�u�����ҕ��S�����v�A�u�����z���v�A�u�����\�Ȕ��W�v�Ƃ��������@�̏�������u���X�N�Ǘ��v�𒆐S�Ƃ���������i�߂Ă����B���Ɂu�\�h�����v�ɂ��Ă͑O�N�x�܂ł�COE�ł��������d�˂Ă��Ă��邪�A�܂��c���ꂽ�_�_�͑����A�Ⴆ�Ώؖ��ӔC�̓]���A�\�h�����̓��������A�i�ׂւ̉e���A���̏������Ƃ̊W�ȂǁA�������ׂ��ۑ�͑����B����ɁA�Ⴆ�h�C�c�ł͏�L�̏���������̉������@���̊�b���Ȃ��h�C�c���@�T�̌������i��ł���B�������ł͂���珔�T�O���A���ۏ��y�ъe���̖@���x�ɂ����鉻�w�����A�C��ϓ��A���R�ی�A��`�q���ϐ������Ƃ������e����łǂ̂悤�ɓK�p����Ă��邩�������̗��_�I�������s���Ă����B |
| ���@��˒� |
| ���@�G���q�@�����b |
���y�[�W��TOP��
| ���Z�E���{�s��Ɩ@ | |
| 6- 1.�@���Z�E���{�s��@�E�S�� |
| �@���{�̋��Z�E���{�s��@���̂�����𑍍��I�Ɍ������钆�j�I�Ȍ����O���[�v�ł���A ���̊��ŋz���ł��Ȃ����𑍍��I�Ɉ����B ���Ƃ���Ǝ��{�s��@���W�̊e�_�I�Ȍ����O���[�v�ƈ�̂ƂȂ��Č����𐄐i����B �����ł͋��Z�R�c��ł̋c�_�������A�ꍇ�ɂ��ΈĂ����B�d�v�ȃp�u���b�N�R�����g�ɉ�����B �����A���{����̎�����Ȃ��ƐR�c�ł��Ȃ���������z����w�͂��s���A ���Ƃ����Z�@�������f�I�E��I�ɍč\��������{�ŋ��Z�T�[�r�X�s��@�̒�āA ���̑��̐��x���v��Ă̂��߂̌������s���B �܂��A���{���������̌��J��Ɩ@�ψ���ɂ����č��肵�����J������Ж@�v�j�ẮA���{�s��̖@�Ƃ��Ă̌��J������Ђ̈Ӌ`�𖾂炩�ɂ�����̂Ƃ��āA���̎������������_�����𐄐i���Ă����B���邢�́A�،�������K�͂̈Ӌ`�A�،�������ɂ����J��Ж@���̊m���Ɋւ�����A���̑��g�s�b�N�I�Ȗ������グ�Ă����B ���Ă̊�ƁE�s��Ɋւ��钲�������O���[�v�Ƃ̋������������{���Ă���B�����S�l��@���H��ψ���Ƃ̌�������̊o���A�����،��Ǘ��ēψ���Ɠ��Ƃ̎O�҂ɂ�錤���𗬋��肪���łɒ�������Ă���A���������瑽��ȕ]���Ă��邪�A������������������ɐ��i���Ă����B |
| ���@�㑺�B�j�@��ёאL |
| ���@������@�،h�V�@���Z�C�@���q�@���r���E�@���G�� |
| 6- 2.�@���Z�E���{�s��@���̃O�����h�f�U�C�� |
| �@�����̑����̌������e�����̍���ߒ��ɂ��������Ȃ�ƑO�����̉e����^�����ƍl������2007�N�̋��Z���i����@�̎{�s�́A���{�ɂƂ��ďd�v�ȑO�i�ł͂��������A�ŏI�I�ɖڎw���ׂ��@�K���V�X�e���̑̌n���炷��A�ꗢ�˂ł����ăS�[���Ƃ͂����Ȃ��B�s��̖@�K���V�X�e���̃C���t�������E���x����K�ɍs���A�s��ɎQ������s���ƃ��[�U�[�̑��ɗ������f�U�C���ɔ��{�I�ɕς��Ă����K�v������B����܂��A���Z���{�s��@��������ɋ@�\���f�I����I�ɍč\�������A�_�\���̓��{�ŋ��Z�T�[�r�X�s��@�K���V�X�e���̃O�����h�f�U�C���̒�Ă��A���킩��₷���A�����\���̍����v���Z�X�̒Ƌ��ɁA�s�������B |
| ���@�����d�m�@�㑺�B�j |
| ���@�،h�V�@���Z�C�@���q�@���r���E�@���G�� |
| 6- 3.�@���ZADR�E�I���u�Y�}�����x���� |
| �@�l�Ȃǂ̋��Z�Ɋւ�����E�����̉����́A���{�ł͍ٔ��ȊO�ɁA�ƊE�^���ZADR�A�ٔ����̒���A�s���^�̍��������Z���^�[�������Z���^�[�Ȃǂ����邪�A����������l�͂ǂ��ɍs���悢�������炸�ǂ����ɑ��k�ɍs���Ă��K�����������I�ȉ����ɂ͌��т��Ȃ��B�ȈՁE�v�����E�_��E��p�̒�������̊ϓ_����A��r�I���z�̋��Z�g���u���ɂ��ẮA����҂͍ٔ����x��I�����Â炭�A����ɑ�������I�ȑI�����Ƃ��āA��O�Ҍ^�́A�����ŃA�N�Z�X���₷���A��I�ŋ@�\���f�I�ȋ��Z���ADR�ɂ�镴���������\�Ƃ��ׂ��ł��邪�A���������D�ꂽ���x�����{�ɂ͂܂��Ȃ��A���哱�ł̐V���Ȑ��x�n�ݒ�Ăւ̊��҂����܂����B2007�N�t�ɗ����グ��ꂽ�A���{�ɂӂ��킵�����ZADR�E�I���u�Y�}�����x�̒��s�����߂̓Ɨ��̔C�Ӓc�̂ł���u���ZADR�E�I���u�Y�}��������v�ł́A����cGCOE�W�҂��Q�����āA����I�Ɍ�����i�߂Ă���B����c�O���[�o��COE�ł́A���̌�������o�[�����ADR�W�҂Ȃǐ��E�e���̐��Ƃƌ𗬁E�������A���ݕ⊮�I�Ɍ����𐄐i���Ă����B�܂������ɁA���̐��x�̔w�i�ɂ���ׂ��AISO�iJIS�j�̋��Ή��E���������V�X�e���̍��ۋK�i�Ɋւ��錤�������s���čs���B |
| ���@�����d�m�@ |
| ���@�،h�V�@���Z�C�@���q�@���r���E�@���G�� |
| 6- 4.�@�A�W�A���{�s��@������ |
| �@2007�N6���ɐݗ����ꂽ�u�A�W�A���{�s�ꋦ�c��iCMAA: Capital Markets Association for Asia, � �o��L�V��, ��\�������ǒ� �����d�m�j�v�ł́A����cGCOE�W�҂��Q�����A���{�ƃA�W�A�̎��{�s������Ƃ⌤���҂��W�܂�A�W�A���{�s��ɂ��Ă̋c�_���s������B����A����cGCOE��CMAA�͑����͂��A���{�ƃA�W�A�ɋ��ʂ��鎑�{�s��̖@�K���V�X�e���E���僋�[�����Ɋւ��錤�����p���I�ɍs���B�u�A�W�A���ʂ̎��{�s��v�Ɋւ���c�_�̃|�C���g�́A�s��W�҂̊Ԃł����܂����L����Ă͂��Ȃ��B�A�W�A�e���͒ʉݎ��̃o���o���ňב֊Ǘ����֘A�Ő����e�������̊J���K�������ʂ̓y�U�͌����ɂ����B�������A1997-98�N�̃A�W�A���Z��@�ȗ��A�A�W�A�̎�v�e���͊e�����{�⒆����s�Ȃǂ̐s�͂Ŋ�@�̍Ĕ���h�����߂̋��͊W��z���Ă����B10�N���o�ĕč����̋��Z��@�ɐ��E�����ʂ��Ă��錻�݁A���{�ƃA�W�A�̌����҂Ǝs������Ƃ��A�A�W�A���ʂ̎��{�s��Ƃ������_�����L���A�e�������K���̘g�g���ăA�W�A���ʎ��{�s��ɓK�p�����ׂ�����K�����[���̃t���[�����[�N�Ȃǎs��C���t���̋c�_���s�����Ƃɂ͑傫�ȈӖ�������B����cGCOE��CMAA�Ƌ��ɁA���[���s��̃v���̎s��Q���҂̂��߂̎���K���̃��[���ƃ��R�����f�[�V�������\�z���Ă���ICMA�ȂǂƂ̌𗬂�[�߁A�A�W�A���ʂ̎��{�s��ɓK�p�\�ȁA�u����c��CMAA���[���u�b�N�v�̍���Ɍ������������s���B |
| ���@�����d�m |
| ���@�،h�V�@���Z�C�@���q�@���r���E�@���G�� |
| 6- 5.�@���Z�v�����V�v���Ɋւ��鑍������ |
| �@�u��`�A�����v�Ɩ��v�����V�v���́A������g�D�A��ƒc�́A�l���A�V���ɍs�����n�߂鎞�ɁA���̍s���̃x�[�X�ƂȂ�w�j�A���邢�͖����������邢�͍���ɑ����������A�Ȃ������s�������ɁA�����Ԃ錴�_���킩��₷�����������̂ł���B����́A�����҂ɂƂ��Đ�ł���ᔻ�̑ΏۂƂ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ���{���̊�{�ł���A�h�炮���Ƃ̂Ȃ��A���邱�Ƃ̂ł��Ȃ��A�A�w���A�N�w�A���O�A�s���K�́iCode of Conduct�j�Ƃ�����B���Z���{�s��@���̃O�����h�f�U�C����A�s��Q���ҁi�ƎҁE���B�ҁE�����ƁE�K���@�֓��j�̍s���K�͂��l����ɍۂ��Ă��A���{�̂���ׂ����ZADR�@�ւ̐��x�n�݂̗��O���l����ɍۂ��Ă��A���{�ƃA�W�A�̎��{�s��̎���K���̂�������l����ꍇ�ɂ��A�v�����V�v���ɂ��Ă̐[�����@�ƌ������������Ȃ��B�������A���݂̓��{�̍���́A�s��ɎQ������e��̂̍s���̔w��ɂ��錴����s���K�͂��A���Ȃ�̒��x�A�{�̖̂ړI�E��|��{������ׂ��v�����V�v�����炩������Ă��܂��Ă��邱�ƂƁA���ꎩ�̂��K���������m�łȂ��A�����̏ꍇ�A�킩��₷�����t�ŕ\�����ꋤ�ʌ���Ƃ��čL�����L����Ă͂��Ȃ����Ƃɂ���B���B�i�p���EEU�j�ɂ�����~�ρi�v�����V�v���Ƃ����Ɋ�Â��č\�z���ꂽISO�K�i�Ȃǁj��č��ł̊֘A�̋c�_���Ɋw�тA����cGCOE�Ȃ�ł͂̋��Z�v�����V�v���Ɋւ��鑍���I�Ȍ��������{����B |
| ���@�����d�m�@�㑺�B�j |
| ���@�،h�V�@���Z�C�@���q�@���r���E�@���G�� |
| 6- 6.�@�t�@���h�@�̑������� |
| �@�����A���Z����A��Ɩ@������ɂ����ăt�@���h�̑��݊��͂���߂đ傫�Ȃ��̂ƂȂ��Ă���B�{���́A���菭���҂̂��߂ɋ��z�Ȏ��Y���^�p����t�@���h�ɂ��A���Ă���������Ă����͂��̌l��s���d���̊�Ɩ@���A���Z�@���̕���������炵�A�����P���ɕ��u���邱�Ƃʼn��ēI���l�ς�s���Љ�̍��ӂȂ������j�I�K�͈ӎ�������Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����ϓ_���d�v�ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B���ɓ������̑劔��Ƃ����T�O�ɑ��ĉ��Ă��ǂ̂悤�ȑΉ������Ă���̂��A�Ƃ��������͓��{�̃t�@���h�@�����ɂƂ��ďd�v�ȈӋ`��L����ł��낤�B���g�̌l���\����J���g���A�A�������̖��ɊS�������o���Ă��邱�Ƃ̈Ӗ����������Ă����ׂ��ł��낤�B |
| ���@�㑺�B�j |
| ���@�،h�V�@���Z�C�@���q�@���r���E�@���G�� |
| 6- 7.�@���Z���i����@�E�A�����J���{�s��@������ |
|
�@���Z���i����@�́A��Ƃ̎������B�ƍ����̎��Y�^�p�Ɏ����邽�߁A����ЁA�����ҁA�����𒇉��Ǝҁi���Z���i����Ǝҁj�̊W���K������@�ł���A��ƂƎs���Љ�Ƃ����ԏd�v�Ȗ�����S���Ă���B���@�̓��e�́A�f�B�X�N���[�W���[�i�J���K���j�A�s��������K���i�s��K���j�A�ƎҋK�����琬�邪�A�ߎ��A�ƎҋK���ɑ傫�ȉ�����������ꂽ�B�܂��A���@�́A�A�����J�̏،����@���@�Ƃ��A���̉e�����x�d�Ȃ�������o���،�����@���AEU�@�̓��������Q�Ƃ��Ĕ��{�I�ɉ�������2006�N�ɐ����������̂ł���B�����Ŗ{���ł́A�������g�D���āA���Z���i����@�̓��e���A�A�����J�@�̓W�J�����Q�Ƃ��A�Ƃ��Ɋ�ƍs���������ɋK�����ׂ����Ƃ����ϓ_���猤��������̂ł���B ���f�B�X�N���[�W���[�� �@�ߔN�A�f�B�X�N���[�W���[�ᔽ�𗝗R�Ƃ��ē����҂�����Ђ₻�̖����̖����ӔC��Njy����i�ׂ��������Ă���A����@�̌`���ɂ���ƍs���ɑ傫�ȉe�����y�ڂ����̂Ɨ\�z�����B�����ŁA�A�����J�̔��ጤ���A�킪���̔��ጤ����ʂ��āA�J���K���ɂ���ƍs���̋K���������ΏۂƂ���B ���s��������K���� �@���ꑀ�c�̋֎~��C���T�C�_�[����̋֎~�́A�s��ɂ�����v���[���[�ł������ЁA�����ҁi�l�����Ƃ���ы@�֓����Ɓj�A���Z���i����Ǝ҂̍s���ɑ傫�ȉe����^���Ă���B�s��������K���́A2006�N�������ɁA�B��傫�ȉ������s���Ȃ���������ł���A�s��������̂�������������邱�Ƃ́A���Z���i����@�̎��̉����̂��߂̏d�v�ȏ�����ƂɂȂ�B�܂��A���Z���i���������Z���i����Ƌ���ɂ���Ƃ�Ǝ҂̍s���̋K���ɓW�J���݂��A����A���̏d�v���������ƍl�����邽�߁A�����̎���K���@�ւɂ�鎩��K���������̑ΏۂɊ܂߂�B ���ƎҋK���� �@�ƎҋK���ɂ́A�Ǝ҂ƌڋq�̊W���K�����鎄�@�I���ʂƁA�Ǝ҂ƍ��̊W���K������s���@�I���ʂ�����B�{���ł́A�O���[�o�������i�ދ��Z�E�����̕���ɂ����ďd�v���𑝂��Ă����҂̑��ʂɒ��ڂ��āA�A�����J�AEU�ɂ�����ƎҋK���̐i�W�݂̂Ȃ炸�A���A�W�A�ߗ����̋ƎҋK���i���{�@���Q�l�Ƃ����W�J���݂���j�Ɣ�r���A�ƎҋK���̂��������������B |
| ���@�����x�Y |
| ���@������@���q�@���r���E |
| 6- 8.�@�f���o�e�B�u����̑������� |
|
���k���@�� �@�m���f�B�b�N�O�����܂ޖk���[���b�p�̊�Ɩ@���𒆐S�ɁA���̖@���x���x���镶���I�E���j�I�w�i�Ȃǂ�������ɓ���A�ߔN���E�I�ɒ��ڂ���Ă��邱�̒n��́A�o�ϓI�E�@���I���ʂ�T������B ���f���o�e�B�u�� �@�ߔN�A�}���ɐi�W�����f���o�e�B�u��Ώۂɂ��āA����ɑ��邠��ׂ��@���x��T������B���ɂ��̗̈�́A�o�ϓI�j�[�Y�E�����̑n�ӍH�v����s���邽�߁A���Ԕc��������ȏꍇ�����Ȃ��Ȃ��A�܂��@���x����ǂ��ɂȂ�P�[�X�������B���̂悤�Ȍ���^���Z���i�E���Z���i����ɑ��ē`���I�Ȗ@�����������ɓK�p�E�W�J���Ă����̂��A�V���Ȗ@������n�o����K�v�����邩�Ȃǂ̖@�I�����̕K�v�������߂��Ă���Ƃ̔F���̂��ƁA�����������L����ƍl�������r�@�I�������܂߂āA���̃v���W�F�N�g�����L���w���E�o�������W�����ƂȂ邱�Ƃ����҂����B |
| ���@������� |
| ���@ |
| 6- 9.�@�ی��_��@�E�ی��Ɩ@���� |
| �@�Љ��ɑΉ����ׂ���100�N�Ԃ�ɕی��_��@���S�ʓI�ɉ�������A���@����Ɨ����ĒP�s�@�Ƃ��Đ��肳�ꂽ�B���̊ԁA�����ۊe�Ђ̂�����ی����s������肪�Љ�I�ɑ傫���̂�グ���A�����̋c�_�ݏo�����B�{��������ł́A���̂悤�ȑ����̖�����݂���ی��@¥�ی��Ɩ@�ɂ��āA�����ҁA�ٌ�m�A�ی������Ƃ̕��X�̂��Q���āA�����ۗ�����ɂ킽��ی��_��@�E�ی��Ɩ@�A����ѕی��̉��߂��߂���ٔ����f�ނƂ��āA���_�Ǝ����̉ˋ���ڎw�����������ጤ�����s���ƂƂ��ɁA�킪���̕ی��_��@���������̉e�����Ă��鉢�ď����Ƃ��A�g��}��A���L���[�݂��������������s�����Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B |
| ���@��ˉp�� |
| ���@ |
| 6-10.�@��ƁE���Z�@�����C���\�z���@���A���ƍċ��� |
| �@�@���Љ��@�ȑ�w�@�\�z�̋N���͂́A�啝�ȋK���ɘa�A���R���ɂ���đ啝�ɕ��������傷����̂Ɨ\�z���ꂽ��ƁA���Z�E���{�s�ꕪ��ɂ������͂��ł���B�������A�@�ȑ�w�@���͂��߂Ƃ��Ă��̐ݗ��ɓ������čő�̐��ƂƂ��ꂽ�͖̂@�N�w�A���@�Ƃ���������̐��Ƃł���A��ƁA���Z�E���{�s�ꕪ��ւ̊S�͏����Ȃ��̂ł������B�܂��A���̕���͎i�@���C�����Ή����Ă��Ȃ���������ł���B�@�ȑ�w�@�͂������i�@���C���I���z���F�Z�����̂ƂȂ��Ă���B���̊��́A�@�����猤���Z���^�[�Ƃ̍������Ƃ��āA���[�X�N�[��OB��@����ʂɑ��āA������@�ւ╔�傩��Ɨ������ƁA���Z�E���{�s��@���Ɋւ��錤���@�ւƂ��āA�����Ė��Ԋ�ƁE���Z�@���i�@���C���\�z���K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ������_�Ɋ�Â����̂ł���B�������A�g�̏�ɉ߂����\�z�ł�����A���炭�͖���Ƃ���������Ȃ��B |
| ���@�㑺�B�j�@���c�O�@�@���Z���^�[ |
| ���@ |
���y�[�W��TOP��
| ��Ɩ@���|���_�E���@�E���߁| | |
| 7-1.�@��Ɩ@�������E�S�� |
| �@�ȉ��̊e���O�̊�Ɩ@���S�ʂɂ��ĒS������B�d�v���ጤ�����Ж@���ߖ��A���@�A�ً}�V���|�W�E�����ɂ��V���N�^���N�@�\��S���B�܂��A�e���ӔC�҈ȊO�̒S���ҁA���_�`���҂ɂ��g�s�b�N�I�Ȋ������S�����ƂɂȂ�B�܂��A�{�������_�̑S�̃V���|�W�E�����̂��̉��f�I�Ȋ����S�����ƂɂȂ�B |
| ���@�㑺�B�j |
| ���@������@�،h�V�@���Z�C�@���q�@���r���E�@���G�� |
| 7-2.�@����c�Ŋ�Ɣ������[������ |
| �@�{������21���ICOE�̒i�K����s���A�������̑����̐��ʂ̍ŏI�ƂȂ���2008�N1���́u����N�^�V���|�W�E���v�ɂĕ��s���A���łɊe�Ȓ����͂��ߑ傫�Ȓ��ڂ𗁂т�Ɏ����Ă�����̂ł���BGCOE�ɂ����ẮA����ɋ�̓I�Ȑ��x�������Č�����i�߂Ă����B�{�v���W�F�N�g�ɂ����ẮA�p���̊�Ɣ����K���ɔ͂�������u���{�Ŋ�Ɣ������[���v�Ă̍쐬���s���A�����āu���{�Ńe�C�N�I�[�o�[�E�p�l���v�n�݂Ɋւ���@������쐬����B����ŁA���B�𒆐S�Ƃ����e���̊�Ɣ����K���̒����ƃq�A�����O���s���A���Ċe���̉�Ж@�E���{�s��@�̗ގ��_�Ƒ���_�̉𖾂�����ɓ��ꂽ�������s���B |
| ���@�n�ӍG�V�@�㑺�B�j�@�͑����� |
| ���@�،h�V�@���Z�C�@���q�@���r���E�@���G�� |
| 7-3.�@�t�����X��Ɩ@������ |
| �@���B�̒��ł��A���[�}�@����ђ����ɂ������i���ƍ��Ƃł������C�^���A�̓`���ڂɈ����p���A ���݂ł��A�����܂ł��Ȃ��h�C�c�ƂƂ��Ƀ��[���b�p�̒��S���߂Ă���t�����X�@��Ώۂɂ��邱�ƂŁA ���[�}�@�ȗ��̖@�̓`����w�i�ɂ��Ȃ���A�����EU�̓W�J�Ƃ����������������āA��ƂƂ������̖̂@�I�ȑ������A ���邢�͊�Ƃ��߂���@�̂�������A����Α��ʓI�A���̓I�Ɍ�������B�����Ώۂ́A��Ж@�A������@�Ȃǂ̓`���I�ȏ��@�̎��_�����ł͂Ȃ��A �����@�A���{�s��@�A��s�@�܂��͋��Z�@�����܂߂��L���Ӗ��ł̊�Ɩ@���S�ʂƂ��A��Ɩ@���̑O��ɂȂ閯�@�A����сA�@�l�̂�������K�肷�錛�@����̎��_�������̑ΏۂƂ���B �[�֎v�z�Ɛl���錾�A�s���v���̒n�A�t�����X�Ŋ�ƎЉ�Ǝs���Љ�͎v�z�I�ɂǂ̂悤�Ȓ��a��ۂ��Ă���̂��A �@�߂̌`���Ƃ�Ȃ����������ƎЉ�̋K�͈ӎ��͉����A��ƎЉ�ł̃t�����X�I�������͉��d������̂Ȃ̂��A �{COE���̖��ӎ��ɂƂ��ėL�v�ȍv�������邱�Ƃ��ł���ƍl���Ă���B |
| ���@���R���� |
| ���@������ |
| 7-4.�@�h�C�c�EEU��Ɩ@������ |
| �@��������ȍ~�̓��{�̖@���x�́A���[���b�p�嗤�̍��A�Ƃ��Ƀh�C�c�̖@���x�̉e�����Đ������ꂽ�B�����́A�A�����J���B���̖@���x�̉e���������Ă���B�������A�A�����J���B����������{�ɂ��邱�Ƃɂ͖�肪����A���̕��Q������Ă���B�\���B�G�g�A�M��������A�������[���b�p�̍��̑�����EU�ɉ����������Ƃɂ���āA���[���b�p�̒n���I���S�͓��ֈړ������B���̌��ʁA�n���w�I�ɂ��h�C�c�͏d�v�Ȉʒu���߂邱�ƂɂȂ����B�����Ƃ��A�h�C�c��EU�̍\�����ł���̂ŁAEU�@�̉e������BEU�́A�Ƃ��Ɍo�ς̃O���[�o��������я��ʐM�Z�p�̔��B�ɓK�������邽�߂ɁA27�J���̉p�m�����W���Ė@���x������������B������������邱�Ƃ͑傢�ɗL�v�ł���B�{�O���[�v�́A��Ж@�i�J���ҎQ���@�����܂ށj�A���{�s��@����у��[���b�p�ٔ����̔�����ΏۂɁA�o�ϓI�E�Љ�I�Ȏ��Ԃɂ����ڂ���������\��ł���B |
| ���@������ |
| ���@ |
| 7-5.�@��ƍs���Ɋ֗^������E�̎��،��� |
|
�@�{�����`�[���ł́ACOE���Ƃ��āA��ƍs���̍��@�����m�ۂ��邤���łٌ̕�m�̖����Ɋւ��錤�������{���Ă����B���̍ŋ߂̊����́A��ƍs���Ɋ֗^����ٌ�m�ƌ��F��v�m�̐��E�ӔC�̂��������������2007�N1��13���̃V���|�W�E���i�G����ƂƖ@�n��4��2��59�ňȉ����Q�Ɓj�ł���BGCOE���Ƃ��ẮA�܂��{�N12���ɁA����̃e�[�}�œ��Ĕ�r���s���V���|�W�E�����J�Â��A���̐��ʂ����\���邱�Ƃɂ���āA����܂ł̊����̏W�听�Ƃ������B �@���N�x����́A�䂪���ɂ����Ă���Ɩ@�����ٌ�m���}���ɐ��������邱�Ƃ܂��āA���̎��Ԃ�c�����钲���v���W�F�N�g�����{�������ƍl���Ă���B���̂��߁A�`�[���̃����o�[���ĕҐ�����\��ł���B���̎��ؓI��Ղ̏�ɗ����āA�䂪���̊�Ɩ@�����ٌ�m�̂���ׂ��������������������ƍl���Ă���B |
| ���@�{��ߐ� |
| ���@ |
| 7-6.�@������|�Y�@������ |
| �@���E�I�Ȍo�ώY�Ƃ̍\���I�ȕω��ɔ����A��Ɠ|�Y�@���A���Ȃ킿��@��ƂɊւ��郊�X�g���N�`�������O�E���[�����������I���o�ώ��Ԃɑ����Đ��x�v���^�p���邱�Ƃ͕K�{�ł���B�O�b�n�d�ł́A�|�Y���x����Ɨ��_�A�t�@�C�i���X�_�̗��ꂩ�猩�Ď��R�Ȏ���𐧖Ă��Ȃ����Ƃ������n����A�Y�ƍĐ��@�\�A�킪���ɂ�����|�Y�@���̗��j�A�č��̃`���v�^�[�P�P�Ƃ����ᔻ����w���i�a�`�g�l���f���j�ɂ��Č������s�����B�{�b�n�d�ł́A���̐��ʂ��܂Ƃ߂A�S�ۂ̂�����ȂNJ֘A�̈�ɂ������L���A�����O���[�v���ł̓��_��[�߁A�O���̗L���҂̈ӌ������܂��āA������|�Y�@�����l���邽�߂̎����𖾂炩�ɂ��Ă䂭�B |
| ���@�⑺�[�@���쑏 |
| ���@ |
���y�[�W��TOP��
| �A�W�A��Ɩ@���A���Z���{�s��@�� | |
| 8-1.�@�A�W�A���ꖯ�����@������ |
|
�@�A�W�A�e���̖@���i���@�j�́A�P�X���I�ɊJ�Ԃ������[���b�p�嗤�@�̉e���������A���̖@�̌n���p���B �������A�A�W�A�Ƃ����Ă��A���ɂ���ēƎ��̕����������A���ꂪ���ʂȌ`�Ŗ@���W�ɉe����^���Ă���B ���̂��߁A����I�ȋK�͂Ƃ������̂��l���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B �������A�Q�P���I�́u�A�W�A�̎���v�ɂ����āA�o�ϓI�Ȃ��������I�𗬂����������Ă��邱�Ƃɔ����āA����@�Ɋւ��铝��I�K�͂̌`���́A����i�ق̉ۑ�ƂȂ��Ă���B �����ŁA����܂ŁA���؊ԁE�����Ԃɂ����Ĕ|���Ă����w�p�𗬂̊W����ՂƂ��āA �V���ɂR���Ԃ̖������@���Ɋւ���u�A�W�A�@�������_�v���`�����A �u�A�W�A����@�̓���I�K�͂Ɠ���I���߂̉\���v��T�邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B �@�܂��A��ƂƎs��ɌW�鑍���@�̈悪��̂ƂȂ��Č����������s�����Ƃ́A ���ꂩ��{�i�I�Ɋ�ƂƎs��ɐ��ޏ����ɒ��ʂ���ł��낤�A�W�A�����ɂƂ��āA �����Ƃ��L�v�Ȓm���������悤�Ɏv����B�{���͂����������_����A ��ƁE�s��@���Ɋւ��āA�����̊e���Ƃ̊ԂɊw��𗬂������������Ă���B |
| ���@�ߍ]�K���@�c�R�P�� |
| ���@���T���Y |
| 8-2.�@�����C�@�����Ɠ��A�W�A�@�� |
| �@�C���Ɋւ���̈�ł́A���ۏ��E���ۓI���K�Ȃǂɂ�铝��I�ȋK�͂��L�����݂��Ă���B���Ƃ����ۊC�㕨�i�^���̕���ł́A���݁A���ۘA����Ƃ��ĐV�������̐��肪��������Ă���ȂǁA�C���Ɋւ��鍑�ۓI�Ȗ@�K�͂ɂ͐₦�ԂȂ��ω����݂��Ă���B�����������ŁA���E���E�i���E�E���j�𒆐S�Ƃ������A�W�A�o�ό��̔��W�͂߂��܂����A���ۓI�@�K�͂̓��A�W�A�ɂ�������߁E�^�p�̓���I�����̕K�v�������܂��Ă��Ă���B���̊��ł́A���������F���Ɋ�Â��āA���A�W�A�𒆐S�Ƃ��鏔�O���̌����҂ƘA�g���A�C���Ɋւ��錤�����͂𐄐i���Ă������Ƃ�ړI�Ƃ���B�@�Ȃ��A�킪���ł́A�C�@�Ƃ����@����̎����I�ȑ��݂͔ے�I�Ȃ������ɓI�ɑ������Ă��Ă���A���Ƃ��ΊC���@�͏��@�̈ꕔ��A�C��ی��@�͕ی��@�̈ꕔ��A�D���J���@�͘J���@�̈ꕔ��A�C�����ێ��@�͍��ێ��@�̈ꕔ��Ƃ����悤�ɁA���f�I�Ɉ����Ă��Ă���B���������ꂼ�ꂪ�e����ɂ����ď����Ȉꕔ��ƂȂ��Ă���B����c��w�ł́A�C�@�𑍍��C�@�Ƃ��ĉ��f�I�ɑ����悤�Ɣ��������C�@������������A���̊��͊C�@�������Ƃ̎����I�ȘA�g��}��Ȃ���W�J���Ă��������B |
| ���@���䐒�j |
| ���@���G�N |
���y�[�W��TOP��
| ���V�A�E�����E�X�J���W�i�r�A�̊�ƎЉ�Ɩ@ | |
| 9-1.�@�k���@�ɂ������ƂƎЉ� |
| �@�d�t��i�����̊�Ɩ@���x�̌����Ƃ����A�ǂ����Ă��p�ēƕ��𒆐S�Ƃ������̂ɂȂ肪���ł���B �������A�m�L�A�̗������悤�ɁA�m���E�G�[��X�E�F�[�f���̂悤�Ȗk�����������E�I��Ƃ�������i�H�ƍ��ł���A �܂��V�F����t�B���b�v�X�Ȃǂ������I�����_�i�ߎ��A�q��ƊE�̓����̓��������ꂽ�j���܂ނ�����x�l���b�N�X�O���A �G�X�g�j�A�Ȃǂ̃o���g�O���A�����Ă��̖k�C�E�o���g�C���Ӎ��̐ڍ�������v�ՂɈʒu����f���}�[�N�ȂǁA ������k���[���b�p�̊�ƎЉ�Ɩ@���x�Ɋւ��錤���́A�킪���ł͂��Ȃ炸�����\���łȂ������悤�Ɏv����B ���ɁA�X�J���W�i�r�A�@���ƌĂ��X�E�F�[�f���Ȃǂ̖@���x�́A ���́u���v�t�ʖ@�w�v���x���镶���Ƃ��ǂ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��@�̈�ł���ƍl������B �܂��h�C�c�@�I�ł���Ȃ���A���O���E�T�N�\�����̌̒n�ł��������Ƃ��v���o������@���x��L����I�����_�A �����ăf���}�[�N�@���i���̓y�ł���A�C�X�����h�@���܂߁j�́A�Ί݂̃C�M���X�@�Ƃ̔�r�������\�ł��낤���Ǝv����B �d�t�@�̈ꕔ�ł͂��邪�A�Ǝ��̖@�̈�Ƃ��āA�k���[���b�p�ɏœ_���i���������O���[�v�𗧂��グ�A ��ƎЉ�Ǝs���Љ�ǂ̂悤�ɋ��������邩�A�Ƃ���COE���_�̖��ӎ��ɔ��錤���������s���Ă���B |
| ���@��������@���V�L |
| ���@ |
| 9-2.�@���V�A�E�����ɂ������ƂƎЉ� |
| �@����c��w�W�̃��V�A�E�����@�̐��Ƃ����p���A���V�A�E�����ɂ������ƂƎЉ�̊W�ɂ��Đ����������������{����B21���ICOE�ɂ����āA���V�A�ō������@�ٔ��������Ƃ̌����𗬂��s�Ȃ������Ƃ܂��āA�܂����V�A�@�̐��Ƃł��郍���h����w�����̏��c��������X�̌������̋q�������ł��邱�Ƃ�����A���̕�����J����l�I�����ƒm���̒~�ς����݂��Ă���B |
| ���@���c�� |
| ���@ |
���y�[�W��TOP��
| ���{�̊�Ɩ@���C�O���M�V�X�e�� | |
| 10-1.�@���{�̊�Ɩ@���C�O���M�V�X�e�� |
| �@���{�̖@���w�̊w�␅���͑����ɍ����A�Ƃ�킯�O���@�������������Ă������{�̖@���w�ɂ͉��ď����ɂƂ��Ă���������Ƃ���̑����Ɛт��~�ς���Ă���B�������A�����������{�̗l�X�Ȗ@��C�O�ɔ��M����邱�Ƃ����Ȃ����߁A�p�A�M�̖@�����x�z���Ă�����̂̓Ǝ��̖@�����������Ȃ����ɂ���M�̌�o��q���Ă��邩�̗l�����悳��邱�Ƃ͐r���⊶�ł���B�{�������ł́A��茤���҂𒆐S�ɐ�啪��Ɋւ���g�s�b�N�����I�ɉp��ŏ�M���s�Ȃ���n���\�z�������ƍl���Ă���B����ɂ͔�r�@���������~�ς��Ă����m�E�n�E���\���Ɋ��p���邱�Ƃ��ł���B�������A�܂��V�X�e���\�z�̂��߂̏����i�K�ł���B |
| ���@�㑺�B�j |
| ���@ |
���y�[�W��TOP��
| �m�I���Y�@�������Z���^�[ | |
| B-1.�@�m������f�[�^�x�[�X�E�m�����_���� |
|
�i�P�j�@�A�W�A�m������p��c�a�̉��B����̒lj��ɂ�锭�W�I�\�z�A���{�E�A�W�A�ɂ�����R�������[�n�E�嗤�@�n�p��̉e���ƒm���@���̌��� �Q�P���ICOE�̒m������iRCLIP�j�ō\�z���Ă��������A�؍��A��p�A�C���h�l�V�A�A�^�C�A�x�g�i���y�уC���h��Ώۍ��Ƃ���A�W�A�m������p��c�a�́A�A�W�A�e���@���x�̌��_�ł���p�ƕ��ɂ̒m�������lj����A�m������DB�ւƔ��W�����B�������ɁA�R�������[���E�嗤�@���Ԃ̑���y�ыߔN�̍��ے��a�̌X�����������A����EU�w�ߍ̑���̉��B���Q�l�ɁA�A�W�A�e���ɂ�����m�I���Y�@���̌p��A�����s�g���a�⍡��̖@���̂�����ɂ��Č�����������B�܂��A�A�W�A�e���ɂ��Ă������������N�V�����lj���[���Ă���B�C���h�ȊO�̃A�W�A�E�I�Z�A�j�A�̉p�ꍑ�������^�Ώۂɉ����A�������͊����̉p��m������c�a�Ƃ̃����N����}���Ă����B���ʂ̔��M�̂��߁A�e���̍u�t�����ق��Ď��^�����f�ނƂ����Ώۍ����Ƃ̌ʃZ�~�i�[�����{���A�Q���҂Ƃ��L���ӌ��������s���Ă���B �i�Q�j�@�w���o���҂Ƃ̈ӌ������ƒm���@���ւ̒� �@�m������p��c�a�̑Ώۍ��e������u�t�����ق����V���|�W�E���⌤�������{�ōs���ƂƂ��ɁA�A�W�A��v���̃��[�_�[�I�����@�֑�w�Ƌ��ÂŁA���n�Ŋw�ҁE�@���W�҂ƁA�i�P�j�̐��ʂ܂��A���{�̉ߋ��̌o������o�ϔ��W�ɂ�����m���̖����⌻��̘_�_�ɂ��ӌ��������s���Ă���B�ŏI�I�ɂ́i�P�j�Ɓi�Q�j�̌����̐��ʂƂ��āA����ׂ��m���@���̒𐢊E�ɔ��M���Ă����B �i�R�j�@�g�����X�i�V���i���m���Z�~�i�[�̎��{ �@�O���[�o���b�n�d�ł���茤���҂̈琬�͎�v�ȃe�[�}�ł���A����E���_�E�����Ƃ���3�{���ẴZ�~�i�[���A�W�A�A���B�A�č��Əꏊ���ڂ��čs���Ă���B�m������DB �Ɏ��^���ꂽ�����f�ނɁA�e�����͌����@�ւ̎�茤���҂ɂ�錤����y�уA�W�A�A�č��A���B�̍ٔ����ɂ��͋[�ٔ����s���B����ɂ��A�L���w����ʂɒm���@�̑��_���r�@�I�ɗ������Ă��炤�ƂƂ��ɁA�ٔ����ɂ������̐��x��m��@���^���A���ے��a�̂��������Ƃ��Ă��炤�B �i�S�j�j���[�X���^�[�A�v�����ł̏�M�ɂ����̋��L�� �@RCLIP�ł͔N�S����{��E�p��Ńj���[�X���^�[�s�������̕��s���A�܂�Web�ł����l�̏�M���s���Ă����B�O���[�o���b�n�d�Ŋi�i�ɖL�x���������ɉ����āA�����̏�M�͂���ɕp�ɂ��[�������Čp�����A���̋��L����}���Ă���B |
| ���@���ї� |
| ���@���얾�q�@�u��T�V�@�ܖ��@�Δ�@���� |
| B-2.�@���ێ���@�ƒm���@�� |
|
�@�v�s�n/�s�q�h�os������A�m�I���Y���̕ی쐅���Ɋւ��鏔���̋K��̒����ƒ��a������I�ɐi���Ƃ͔ے肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�������A�e���̒m�I���Y�Ɋւ��邻�̑��̎����@�K����݂�Ɗe���̎Y�Ɛ���╶������̑���f���ĈقȂ邱�Ƃ������A�����̎����I�s�g�̓_�ɂ��Ă͎c���ꂽ���_�������B �@�����ŁA�m�I���Y���̍��ۓI�ی���������邽�߂̈���@�Ƃ��āA���ۍٔ��NJ����A�����@�A�����̏��F�E���s���܂ޒm�I���Y���Ɋւ��鍑�ێ��@�̋��ʌ�����T�����悤�Ƃ��錤���v���W�F�N�g��������B����ł́A�A�����J�@������iALI�Ɨ�����j�́A�Q�O�O�Q�N�S������u�������z�����m�I���Y�����Ɋւ���ٔ��NJ��A�@�I���y�є����Ƀ`�F�N�p����錴���v��Ǝ��̃v���W�F�N�g�Ƃ��ĔF�߁A�j���[���[�N��w��Ruchelle C. Dreyfuss������R�����r�A��w��Jame C. Ginsburg�����𒆐S�ɍ�Ƃ�i�߁A�Q�O�O�V�N�T���P�S����ALI����ō̑�����A�Q�O�O�W�N�U���ɂ��̓��e���o�ł���Ă���B�����ł́A�h�C�c�̃}�b�N�X�v�����N���c�́A�Q�O�O�P�N�Ƀ}�b�N�X�v�����N���̍��Y�������Ō`�����ꂽ��ƃO���[�v�W�����āA�Q�O�O�T�N�ɐ헪�I�v���W�F�N�g�̈�Ƃ��ē��l�Ȗ��ɂ��ă��[���b�p�̑�����̑��Ă��܂Ƃ߂��Ƃ��J�n�����B �@�������̌����́A�Q�O�O�S�N�Q���̓��{�Ɗ؍��̍��ێ��@�E�m�I���Y�@�̌����҂𒆐S�Ƃ������ۃV���|�W���E�����_�@�Ƃ��āA������̃v���W�F�N�g�̐��ʂ܂��Ȃ���A����ɒ����̍��ێ��@�w��Ƃ����͂��Ȃ��瓌�A�W�A�̎��_����m�I���Y���Ɋւ��鍑�ێ��@��̋��ʌ�����T�����Ă����B�����āA����́A�����̌����Ŗ��炩�ɂ��邱�Ƃ��ł��鋤�ʌ�������b�Ƃ��Ȃ���A���A�W�A�ɂ�����Z�p�ړ]���x�\�z�ɂ������@�Z�p�I�����������邱�Ƃ�ڎw���Ă���B |
| ���@ |
| ���@�����@���m�� |
���y�[�W��TOP��
| ��ƁE��v�V�X�e�������Z���^�[ | |
| C-1.�@��Ɠ����̌o�ϕ��� |
|
�@21���I�ɂ������ƎЉ�̂�������l����ɂ������ẮA��ƂƂ�����Ƃ�܂��l�X�ȍ\�����i����A�]�ƈ��A�����A�ڋq�A�n��Љ�Ȃǁj�̍s���Ƃ��̊W�i�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�j���l�@���邱�Ƃ��s���ł���B�����āA���L���ȃR�[�|���[�g�E�K�o�i���X����������邽�߂ɂ́A�����Ȃ�@���K�v�ƂȂ�̂�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɁA�����̍l�@��ʂ��ē��{�̊�ƎЉ�ɂƂ��ĕK�v�Ȑ��x�\�z�̎��_����邽�߂ɁA�e���̕����I�A���j�I�w�i���\���ɍl��������ŁA�s���Љ�Ŋ�Ƃ��ʂ����ׂ������͉����A�����Ă���͍����Ƃɂǂ��Ⴄ�̂���T�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B���̈Ӗ��ŁA�{�����̕��@�́A�{���_��1�̓����u�s���Љ�̂�����A���̔w�i�ɂ���v�z����j�A�N�w�����ΏۂƂ���@�艺�����������s���A����܂��Ă���ׂ��p��T������v�ɂ��������̂ł���B�e���̕����A���j�A���K���l���ɓ��ꂽ�A�A�����J�^�ł͂Ȃ��R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�̃��f���𐢊E�Ɍ����Ē���Љ�I�Ӌ`�͂���߂đ傫���ƍl������B �@�����������ϓ_����A�{�v���W�F�N�g�ł́A���{��Ƃɂ������Ɠ����\���ƁA��ƍs���A�p�t�H�[�}���X�̊W���o�ϊw�A��Ƌ��Z�̗��ꂩ��A���ؓI�ɕ��͂��A����̖]�܂�����Ɩ@���E���{�s��@���̂�����ɂ��Čo�ϊw���Ƌ��Z�_����̃C���v���P�[�V���������B��̓I�ɂ́A�ϖe������{��Ƃ̓����\���̎��Ԃ𖾂炩�ɂ��A���̓�������ƋƐт��ƍs���ɗ^����e���ɂ��ĕ�I�ɕ��͂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B�ȏ�̖ړI�ӎ��ɗ����āA�u��Ɠ����̌o�ϕ��́v�ǂ͊�ƃf�[�^�x�[�X�̐����A�f�[�^�x�[�X�����p�������ؕ��͂𒆐S�ɐi�߂�B |
| ���@�{���p���@�v�ۍ��s�@�L�c�^��@�a����_ |
| ���@�����N���Y |
| C-2.�@��Ɗ����̕ϗe�ƊJ���E��v�E�č��E�������� |
|
�T�@�u���ۍ�����̊T�O�t���[�����[�N�v �O���[�o�������i�ސ��E�̎��{�s��̒��ŁA��v��̍��ۓI��convergence�͍ŏd�v�ۑ�̈�ɂȂ��Ă���B���������̂�����́A���E�e���ŕK��������l�ł͂Ȃ��B���{�s��̃O���[�o�����ƍ����s��̋K���Ƃ̃o�����X��ۂ��Ȃ���A�Љ�K�͂Ƃ��Ẳ�v����o�ώЉ�̕ω��ɑΉ������ă����e�i���X���Ă������Ƃ́A�������₷�����Ƃł͂Ȃ��A���ɁA�����̉�Ж@��Ŗ@�Ƃ̊W�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A����A��v���convergence�Ƃ������E�I�Ȃ��˂�i�����j�̒��ō��ۍ�����iIFRS�j��������Ƃ��č̗p���鍑�͊ԈႢ�Ȃ���������ł��낤�B �o�ώЉ�̕ω��ɍ�����IFRS�����肵�A���肵�Ă�����ƃv���Z�X�ɂ����ĉ������������߂���̂́A���ł�due process�ł���B�����ɂ����āA�e���̐����I�Ȏv�f�z���Ē��S�I�Ȗ������ʂ�������̂́A��v�̊T�O�t���[�����[�N�Ɋւ��鐢�E�I�ȃR���Z���T�X�������đ��Ȃ炸�A�{�����ł́A�ȏ�̂悤�Ȗ��ӎ��Ɋ�Â��āA����3�̍�Ƃ𒆐S�Ƀv���W�F�N�g��i�߂�B�@���E�e����IFRS�̓K�p���ԂɊւ��鐳�m�ȏ������W�A�AIASB�̊T�O�t���[�����[�N�E�v���W�F�N�g�̐��ʂȂ�тɋߔN��IFRS�L���^�C�����[�ɏ����W�A�B��L�A�̏��𑊑Ή����ĕ��͂����Ƃ�ʂ��A�����v�̊��ɉ������T�O�t���[�����[�N�𖾂炩�ɂ���B �U�@�u��v����̊�b�v ��L�T�̃e�[�}����������ۂɂ́A��v���x�Ƃ͋�����u������v�ɂ�����u�F���Ƒ���v�̖{���I�ȈӖ��𖾂炩�ɂ��錤�����������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���̌������ʂ����W���Ƃ��Ă͂��߂�IFRS�Ȃ�тɂ����ɒʒꂷ��T�O�t���[�����[�N�𑊑Ή����đ����邱�Ƃ��\�ɂȂ邩��ł���B �u�č��ɂ�������^��`�̌����v(Professional Skepticism in Auditing) �@�u�ǂ̂悤�Ɋč������{����A�o�c�҂ɂ��s���ȍ������č��l�͌��o���邱�Ƃ��ł���̂��v�Ƃ����e�[�}���A�č��l�̖����E�č��l�̐ӔC�Ɗ֘A���āA���Ɋ�{�I�Ȗ��Ƃ��ĕ��サ�Ă���B���̖��̔w��ɑ��݂����{���A���ꂪ���^��`�ł���B�č��ɂ�������^��`�Ƃ́A�č��l�̐S�̖���p���ɉ߂��Ȃ��̂��A����Ƃ��A�č����f�Ɋւ����{�I�Șg�g�݂�������̂ł���̂��B���̃e�[�}���p���I�Ɏ��g�݁A���{���F��v�m����E�č��@�l�̋��͂����߂A�ŏI�I�ɋ����̌������ʂ����\�������B |
| ���@�ҎR�h�q�@���H���p�@�쑺�`�� |
| ���@ |
| C-3.�@�m���ƃC�m�x�[�V���� |
|
�@���l��n�o���邽�߂̒m���}�l�W�����g���V���ȋǖʂ��}���Ă���B�Z�p�̍��x���ƕ��G���ɂ��J���R�X�g�������������ŁA���i���C�t�T�C�N���͒Z�������Ă���B�����J����̐L�ї�������グ�̐L�ї�������悤�Ȏ��Ԃ��������Ă���A�J���R�X�g���������r�W�l�X���f���̊m�����}���ł���B �@�����ŋ��߂���̂��A�I�[�v���C�m�x�[�V�����̔��z�ł���B�]���̃N���[�Y�h�^�̎d�g�݂ł́A�����J�����琻�i���E�̔��܂ł��ׂĎ��O��`�ōs���̂��ʏ�ł���B�������A���̎d�g�݂ł͓��Y��Ƃ̃r�W�l�X���f���ɓK�����Ȃ��Z�p��m���̑����͖����p�̂܂ܕ��u����Ă��܂��B����͎Љ�I�����ł�����B�ނ���A���Ђփ��C�Z���X������A�X�s���I�t���ĕ���������A���邢�͔��p����Ȃǂ��Đ헪�I�Ɋ��p���ׂ��ł���B �@���̂悤�Ȗ��͐����ƂɌ��������̂ł͂Ȃ��B�R���e���c�Y�Ƃł��A���{�ŊJ�����ꂽ�L�����N�^�[���č��Ȃǂʼnf�扻����Ă��邪�����ȃ��^�[�����l�����Ă���Ƃ͂�����B�]���̐��������^�̉��l�n���E�l���̎d�g�݂��������A�m�����L���Ɋ��p�����悤�Ȑ��x��d�g�݁i�m���̕]���A�m���̒���s��j���\�z���ׂ��ł���B�o�c����̌����O���[�v�Ƃ��ẮA�m���̊��p��O���ɒu�������x�v�ɉ��炩�̃C���v���P�[�V�����������ƍl���Ă���B |
| ���@���c���@���B�F�@�J���^�� |
| ���@�g�V���l |
| C-4.�@���{�̊�Ɠ����F���j�I�p�[�X�y�N�e�B�u |
|
�@�{�v���W�F�N�g�̖ړI�́A21���ICOE�v���O�����̐��ʂ��p�����A1900�N���猻�݂܂ł̖�1���I�ɂ킽����{��Ƃ̊�Ɠ����\���Ɗ�ƍs������уp�t�H�[�}���X�̊W�ɂ��Ă���ɍ������x���̎��ؕ��͂��s���A���ꂩ��̓��{�̊�Ɩ@���Ǝ��{�s��@���̂�����ɂ��Čo�ϊw�I�ɂ��[���C���v���P�[�V��������邱�Ƃł���B �@21���ICOE�v���O�����ɂ����ẮA����̓��{�̖]�܂������x�v�̓W�]��ړI�ɁA��Ɩ@���E���{�s��@���Ɗ�ƍs���̊W�Ɋւ�����ؕ��́A��̓I�ɂ́w����c��w�����}�C�N���f�[�^�x�[�X�x��p�������{�̓����ƕی�@���̗��j�I�W�J�A���及�L�\���Ɗ�ƃp�t�H�[�}���X�A��O�����{�ɂ������Ɠ����̓����Ƃ��̗L�����A����ɑO�v���O�����̍ŏI�N�x����\�z���n�܂����w����c��w����M&A�f�[�^�x�[�X�x�Ɋ�Â���O�����{��M&A�Ɋւ��錤�������{����A���ꂼ��̐��ʂ�COE�p���Ɍ��������B �@�{�v���W�F�N�g�ł́A��L�̌����e�[�}�ɂ��āA���۔�r�̎��_��V���Ɏ�����邱�ƂŁA�܂��@������̐��ƂƂ̋�������������܂ňȏ�ɐϋɓI�ɍs�����Ƃɂ���āA��w�̐[���E������}���Ă��������B�܂������̐��i����я[���Ɍ������Ȃ��e�f�[�^�x�[�X�̊g�[���s���A�O���[�o��COE�v���W�F�N�g���Ԓ��̊w�O���J�������������B���j�I���_�������ꂽ���ؕ��͂̒~�ς́A���݂���я����̓��{�ɂ�����]�܂�����Ɠ����̂�������ƂƊ�Ɩ@���E���{�s��@���Ƃ̊W���l�@�����ł��[���C���v���P�[�V������^������̂ƂȂ낤�B |
| ���@�{���p���@�Ԉ�r��@�ē��� |
| ���@ |
���y�[�W��TOP��
|
COPYRIGHT ����c��w�O���[�o��COE�v���O�����@<<��Ɩ@���Ɩ@�n��>>���������� Allrights Reserved. Global COE, Waseda Institute for Corporation Law and Society. |