 |
||
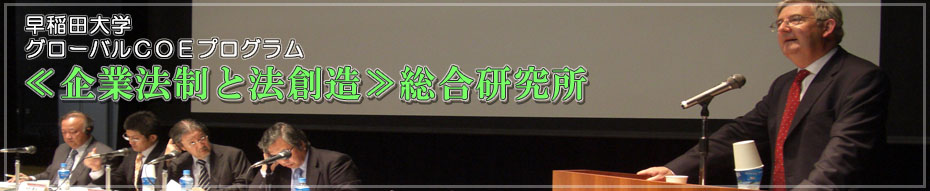
| - ご挨拶 | ||
| - グローバルCOEとは | ||
| - 研究体制 | ||
| - 組織体制 | ||
| - 事業推進担当者 | ||
| - 研究プロジェクト | ||
| - 研究論文(叢書) | ||
| - 季刊 企業と法創造 | ||
| - イベントレポート | ||
| - 研究会履歴 | ||
| - 出版・刊行物・論文 | ||
| - お問い合わせ | ||
| - ニュースレター | ||
 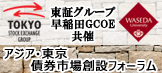 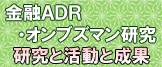 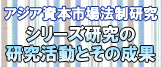  中間プレゼン資料 |

『季刊 企業と法創造』は、Webにて閲覧可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
21世紀COE叢書『企業社会の変容と法創造』
 第1巻 企業・市場・市民社会の基礎法的考察
第1巻 企業・市場・市民社会の基礎法的考察第2巻 企業の憲法的基礎
第3巻 民法理論と企業法制
第4巻 企業法制の現状と課題
第5巻 企業活動と刑事規則
第6巻 労働と環境
第7巻 知的財産法制の再構築
第8巻 企業統治分析のフロンティア
法創造の比較法学―先端的課題への挑戦
(2010年7月出版、572ページ、ISBN978-4-535-51779-0、税込価格7,980円、発行:日本評論社)
戒能通厚・石田眞・上村達男 編

| アメリカの民商法システムを市民法原理から批判的に再検討し、西欧法の継受を吟味しつつアジアでの法システムの再構築を追求する。 | ||||||||||||
| はしがき(戒能通厚) 総論 [上村達男] 第1部 新世紀における比較法の理論
第2部 法創造の比較法学 国際シンポジウム「法創造の比較法学-新世紀における比較法研究の理論的実践的課題」 シンポジウム1 比較法の新時代――市民社会と法の調和を求めて [趣旨説明][戒能通厚] 1 日本民法改正事業と比較法[内田 貴] 2 法制史と比較法[Reinhard Zimmermann] 3 ひとつのヨーロッパ民法典に関する哲学[Hugh Collins] 4 ベトナムにおける民法の法典化[Nguyen Ngoc Dien] 5 東アジアにおける西洋法の継受[陳聡富] [パネル・ディスカッション] シンポジウム2 グローバル経済危機と労働法の役割――国際比較を通じて [趣旨説明][石田 眞] 1 イギリス報告[Hugh Collins] コメント:[石橋 洋] 2 アメリカ報告[Karl Klare] コメント:[林 弘子] 3 イタリア報告[Bruno Caruso] コメント:[大木正俊] 4 デンマーク[Ole Hasselbalch] コメント:[和田 肇] 5 韓国報告[盧尚憲] コメント:[根本到] 6 日本からの問題提起[島田陽一] コメント:[毛塚勝利][菊地馨実] [成果と課題][石田 眞] |
||||||||||||
Grand Design for an Asian Inter-Regional Professional Securities Market (AIR-PSM)
(2008年3月31日出版、98ページ、ISBN978-4-8419-0493-2、税込価格4,725円、発行:レクシスネクシスジャパン)
犬飼重仁 編著
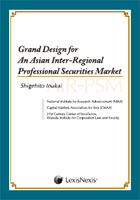
| 総合研究開発機構と早稲田大学COEの共同研究の成果である本書は、2007年3月に刊行した『アジア域内国際債市場創設構想』から中核的論文を抜粋し、さらにその後の研究から「アジア・インターリージョナル・プロフェッショナル・セキュリティーズ・マーケット(AIR-PSM)」に関する成果などを加えて、文章を改訂、英語に翻訳したものである。 アジアでは、近年、域内の発展と競争力確保のために、国際的金融市場を積極的に作り出すことが基本的に可能な状況となりつつある。この作り出されるべき国際的金融市場は、域内に自由な取引環境を備えたプロの参加者のための市場である「ユーロ債市場」のようなものが想定されている。来るべきアジア域内の国際的金融市場創設の際、中核の市場インフラとなるのが、今回提言した「アジア・インターリージョナル・プロフェッショナル・セキュリティーズ(Asian Bond)市場」である。 現在まで、アジア域内主要国の国内金融資本市場では、関連の法規制や決済システムなどの市場インフラ構築が進みつつあるが、それに対し、国際債が発行され売買流通される場としての、アジア域内で自己完結する「共同のオフショア市場=AIR-PSM」の発達は、決定的に遅れている。そしてその必要性すらあまり認識されていない。 したがって、その必要性について提言するとともに、それを可能とするための方法とプロセスについて、今後、広くアジアの市場関係者との議論を活性化させるため、前提となる基本認識について提言を行うことが重要であると考えて刊行されたのが、本書である。 ここでは、そのAIR-PSMの創設のための必要条件と、同市場へのロードマップを提言している。 |
犬飼 重仁 |
日本版金融オンブズマンへの構想 認定投資者保護団体制度を生かす道(2007年11月1日出版、302ページ、ISBN978-4-8419-0469-7、税込価格2,940円、発行:レクシスネクシスジャパン、発行:雄松堂出版)
犬飼重仁・田中圭子 編著

| 本書は、2007年施行の金融商品取引法で新設された認定投資者保護団体制度を生かしつつ、日本に今後必要となるであろう「日本版金融オンブズマン制度」の構築に向けたラフなグランドデザインと、その手本となるべき英国の制度などについての情報をまとめたものである。 早稲田大学COEとNIRAは、平成15(2003)年度から共同で「法と市場と市民社会のあり方に関する研究」を実施。その成果として2005年に「日本版金融サービス法規制システムのグランドデザイン提言』を発表した。 その包括提言は、金融庁法制化担当官等により詳細に参照され、提言内容が法制度に実際に反映されて、様々な面で金融商品取引法に生かされている。金融ADR・オンブズマン制度に関する提言はそのひとつであるが、具体的には、本書のタイトルにもあるように、金商法における認定投資者保護団体制度の創設として結実した。 さらに、我国に必要となる本格的な日本版金融オンブズマン制度の創設検討に関しては、2006年3月13日の政策フォーラムにおける英国金融オンブズマントップ2名の講演を契機としているが、その記録をはじめ、必要な情報が本書におさめられている。 また、2007年4月18日には、「金融ADR・オンブズマン制度構築への展望」と題する政策フォーラムが実施され、早稲田/NIRAの共同研究の途中経過を報告したが、そのフォーラムの開始直前に、同様の認識と展望を共有するフォーラム参加者を中心に「金融ADR・オンブズマン研究会」が設立され、第一次提言を発表した。 本書は、その提言内容も含め、関係の弁護士諸氏や法務省・法テラス関係者、学者・研究者などの協力も得て、2007年時点における制度の状況とあるべき制度理解に必要不可欠な内容を纏めたものである。 すなわち、わが国に金融ADR制度を創設していくに際して、金融機関など関係者に対する啓蒙のために最適の報告書となるものであるところ、実際に本書は、消費者行政や金融行政に明るい国会議員や研究者、官庁等の関係者によって詳細に参照された。 本書は、「金融ADR・オンブズマン研究会」との相互協力によってまとめられた中間報告ともいえるものであるが、この内容を基にして、同研究会では2008年11月に、より具体的な制度モデルの提示を行うべく、「金融オンブズマン機構提言」を発表。本書と同提言は、金融庁及び金融審議会委員等により詳細に参照され、2009年の、いわゆる「金融ADR法」制定に繋がる、重要な契機となったということができる。 |
犬飼 重仁 |
変貌する日本企業の統治構造:制度変化と組織的多様性
Corporate Governance in Japan-
Institutional Change and Organizational Diversity
(Oxford University Press より2007年9月出版, 416 ページ, 23.5x15.5cm, 978019 9284511 税込価格 13,125 円)

| 本書は、独立行政法人経済産業研究所のコーポレ-トガバナンス研究グル-プの共同研究の成果である。各章は、内外の第一線の経済学、社会学、法学者によって執筆され、全体として日本企業の統治構造の変容の全貌がわかる構成となっている。日本企業の組織と行動に関心をもつ研究者、さらに、日本企業の今後の新たな「かたち」に関心をもつ実務家の方々にも是非本書を手にとってもらいたい。 |
宮島 英昭 |
株式会社はどこへ行くのか(2007年8月24日出版、 四六判上製・368ページ、 ISBN978-4-532-31325-8、1,680円(税込)、 日本経済新聞出版社)上村達男・金児 昭 著
本書は、株式会社と資本市場に関する最新のトピックをほぼすべて織り込んで、基礎理論に立ち返った考察を加えておりますが、そこには企業と市場と市民社会というキーワードを法分野横断的に共有するという本研究所での研究の成果が大幅に反映されております。そうした観点からも、本書をお読みいただけましたらまことに幸いです。

| 序 章 | 暴走する株式会社を食い止めよ |
| 第1章 | 誰のために会社はあるのか |
| 第2章 | 便利で危険な株式会社とは何か |
| 第3章 | 公正な証券市場に求められる規律 |
| 第4章 | 人間中心の企業社会の構築へ |
| 終 章 | 会社法改革は終わらない |
| 巻末追補 | ブルドックソース事件最高裁決定 |
| あとがき | 対談を終えて |
「ブルドックソース株主総会決議禁止等仮処分申立に対する『幻の』意見書」
ここに公表する意見書は、スティールパートナーズによる公開買付に対抗してブルドックが導入した買収防衛策の効力を巡って争われ件について、ブルドックの代理人からの要請によって作成した意見書であります。しかし、この意見書はついに東京地裁にも東京高裁にも提出されませんでしたので、「幻の意見書」となりました。私の意見書の基本的構成は東京高裁の見解に近く、会社法の議論よりも株主の属性の問題が最優先されるべきというものです。相手の筋が悪いから肯定されるというというような問題を会社法理論上当然であるかに構成することは、会社法の劣化を招くことを恐れたものであります。いずれにしましても、意見書を書きながら提出されなかったという経験は初めてのことであり、公表を予定して書いたものでありますので、ここに公表させて頂く次第であります。
日本のM&A―企業統治・組織効率・企業価値へのインパクト(2007年7月出版、 A5判 上製、404頁、ISBN:978-4-492-39484-7、3,990円(税込)、東洋経済新報社)編著:宮島 英昭
90年代後半、なぜM&Aは急増したのか。M&Aは本当に企業価値を向上させたか。そして日本経済にどんなインパクトを与えたかを、実証分析やケーススタディを使って明らかにする。

| 序章 | 増加するM&Aをいかに読み解くか―分析視角と歴史的パースペクティブ/宮島英昭 |
| 第1章 | M&Aはなぜ増加したのか/蟻川靖浩、宮島英昭 |
| 第2章 | 外資によるM&Aはより高いパフォーマンスをもたらすのか/深尾京司、権赫旭、滝澤美帆 |
| 第3章 | メガバンクの誕生―市場はいかに評価し、効率性はどう変化したのか/家森信善、播磨谷浩三、小林毅 |
| 第4章 | 完全子会社化はどのようなときに行われるか/菊谷達弥、齋藤隆志 |
| 第5章 | 従業員の処遇は悪化するのか―M&Aと雇用調整/久保克行、齋藤卓爾 |
| 第6章 | どの企業が敵対的買収のターゲットになるのか/胥鵬 |
| 第7章 | グローバル競争優位の構築と転移―日本電産のM&A戦略/渡邉渉、天野倫文 |
| 第8章 | 統合フルサービス化による補完性の実現―通信部門のM&A/神野新 |
| 第9章 | 相互学習による価値の向上―自動車産業におけるM&A/ダニエル・アルトゥーロ・ヘラー、藤本隆宏 |
| 第10章 | 大胆な事業売却―雪印の経営再建戦略/柳川範之、大木良子 |
| 終章 | 日本のM&Aの国際的特徴と経済的機能は何か―本書の総括と展望/宮島英昭 |
企業犯罪とコンプライアンス・プログラム(2007年4月10日出版、A5版・335ページ、ISBN:9784785714215 (4785714212)、3,570円(税込)、商事法務)田口 守一・甲斐 克則・今井 猛嘉・白石 賢【編著】
内閣府経済社会総合研究所との研究協力で、日本の主要企業3千社に対し、企業倫理やコンプライアンスに関する実態調査研究を行い、その内容を出版物として発行いたしました。
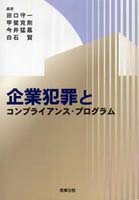 第1部 企業の社会的責任(企業の社会的責任と新たな(刑事)法システムの構築―アンケート調査・シンポジウム・訪問調査を終えて
「シンポジウム」企業の社会的責任)
第1部 企業の社会的責任(企業の社会的責任と新たな(刑事)法システムの構築―アンケート調査・シンポジウム・訪問調査を終えて
「シンポジウム」企業の社会的責任)第2部 企業犯罪に対する刑事責任とコンプライアンス・プログラム(コンプライアンス・プログラムと企業の刑事責任;企業の意思決定過程における企業体質・企業文化と企業責任;組織体の処罰―コンプライアンス・プログラムをめぐる議論を踏まえて;コンプライアンス・プログラムと企業過失;公益通報者保護法と刑法;企業の犯罪被害回避とコンプライアンス・プログラム;「コンプライアンス」の現在と不祥事防止;企業犯罪に対する刑事手続;課徴金減免制度の法的性格)
第3部 資料―「企業の社会的責任・コンプライアンス等に関するアンケート調査」調査票・アンケート分析資料
法の基本概念のexplicatioとKritik(2007年4月発行、A5版・406ページ)
「基本的法概念のクリティーク」研究会(企画グループI-b)により研究成果としてまとめられました。
別冊NBL116-知財年報 I.P. Annual Report 2006-

特集:知的財産保護の拡がりとその交錯
(2006年12月刊行、B5判・358ページ、ISBN4-7857-7088-0 、4,200円(税込)、商事法務)
渋谷達紀、竹中俊子、高林龍 編
1年間に公表された知的財産法に関する判例や論文の解説の2006年版。本書は判例・学説・動向をはじめ「知的財産権の広がりとその交錯」を特集としてあらゆる知的財産法領域に係わる問題を広く取り上げて論文も収録する。研究者、実務家に役立つ一冊。
別冊NBL 106 知財年報-I.P. Annual Report 2005-(2005年11月刊行、B5判・321ページ、ISBN4-7857-7078-3 、3,885円(税込)、商事法務)渋谷達紀、竹中俊子、高林龍 編
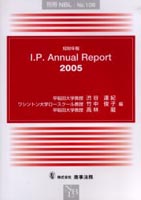
| 知的財産法をめぐる情報のエッセンスをまとめる知的財産年報2005年版。1年間に公表された判例、論文を紹介するとともに産業界、国際的な動きや話題となっているテーマの論説等も取り込む。 |
図解入門ビジネス知財信託の基本と仕組みがよーくわかる本 (単行本)
COE研究所渡辺宏之准教授(著)
(2005年7月10日出版、A5版・191ページ、ISBN9784798011011、1,890円(税込)、秀和システム)

2004年12月に行われた信託業法の改正は、1922年の同法制定以来、82年ぶりの抜本改正で、金融機関以外にも信託業への参入が解禁されました。このほか、金銭や不動産に限定されていた信託の対象に、著作権や特許権などの知的財産権も加わり、「知的財産権の信託」が解禁されました。信託業法の改正により、企業の資金調達手段が広がり、新たなビジネスチャンスが生まれました。 |
渡辺 宏之 |
包括的・横断的市場法制のグランドデザイン
「日本版金融サービス市場法」制定に向けての提言
NIRA(総合研究開発機構)との共同研究を行い、当研究所上村達男所長を座長として他大学COE4拠点のリーダーを含む官・学・民の専門化がメンバーとして参加し、「法と市場と市民社会のあり方に関する研究会」を行い、その成果を3分冊に取りまとめました。共同研究の成果は2004年7月NHKで放映されました。

(1) 総論編「日本版金融サービス市場法制のグランドデザイン」(2005年5月21日発行、A5判・384ページ、ISBN 4-7955-3509-4、2,100円(税込))
(2) 各論編「包括的・横断的な市場法制の確立に向けて個別論文集」(2005年6月1日発行、A5判・392ページ、ISBN 4-7955-3510-8、2,100円(税込))
(3) 海外事例編「金融サービス市場法制の核心を欧州と英国に学ぶ」(2005年6月11日発行、A5判・336ページ、ISBN 4-7955-3511-6、2,100円(税込))
論文
平成22年度
渡辺宏之(COE専任教授)
「Designing a New Takeover Regime for Japan: Suggestions from the European Takeover Rules」(MAX-PLANCK-INSTITUT FURPRIVATRECHT・独日法律家協会編『ZJAPANR J.JAPAN.L. JOURNAL OF JAPANESE LAW』91頁以下 2010年
平成18年度
上村達男
「証券取引法との統合」『企業会計特別保存版 新会社法詳解』 2006年 7月 中央経済社
「商法・証券取引法における不法行為」『法律時報』78巻8号 2006年 7月 日本評論社
「新会社法の性格と法務省令」『ジュリスト』1315号 2006年 7月 有斐閣
「村上ファンドはなぜ挫折したのか」『世界』755号 2006年 8月 岩波書店
「新会社法の性格と会社法学のあり方」森=上村共編著『会社法における主要論点の評価』 2006年12月 中央経済社
高林龍
「無効判断における審決取消訴訟と侵害訴訟の果すべき役割」『別冊NBL・知財年報』116号 商事法務
崔成俊・清水節・高林龍「韓国の知的財産権判例の最新の動向」『別冊NBL・知財年報』116号 商事法務
「東アジアにおける産業財産権関連紛争の裁判上の処理に関する実態調査」『知財研フォーラム』66号 10頁 財団法人知的財産研究所
木棚照一
「特集 日韓比較・国際知的財産法研究(3)」『季刊 企業と法創造』第7号
「知的財産侵害訴訟における準拠法 -知的財産の種類による準拠法の異同などに関する立法問題を中心に-」『季刊 企業と法創造』第7号
「日本と韓国間における国際相続法に関する法的問題」『戸籍時報』596号 2006年 4月 15-26頁 日本加除出版
宮島洋
「租税政策の諸問題と執行面の課題」『税経通信』61巻12号 2006年 9月 17-26頁 税務経理協会
「近年の租税・税制論および税制改革の展開とその背景」『財政と公共政策』28巻2号 2006年10月 78-94頁 京都大学財政研究会
宮島英昭
「企業再構築研究調査事業『平成18年度皮革産業振興対策調査等報告書』」報告書(代表) 経済産業省
「M&Aの経済分析:M&Aはなぜ増加したのか」『RIETIディスカッションパーパーシリーズ06-J-034』 2006年 4月
「日本型取締役会の多元的進化」神田秀樹他編『企業統治の多様化と展望』 2006年 5月 金融財政事情研究会
「急増するM&Aをいかに理解するか:その歴史的展開と経済的役割」『RIETIディスカッションペーパーシリーズ06-J-044』 2006年 6月
加古宜士
『会計基準のコンバージェンスに向けて(意見書)』金融庁企業会計審議会 2006年 7月
『国際競争力を高める企業会計制度』会計情報 第360号 2006年 8月
『会計基準の国際統合-わが国の制度的対応-』 2007年 2月 中央経済社
内田勝一
「民法・戸籍法・不動産登記法」『判例タイムズ』1204号 4頁 判例タイムズ社
「平成17年度重要判例解説」『臨増ジュリスト』1313号 2006年 6月 有斐閣
宮澤節生
「プロブレムブック 法曹の倫理と責任 第2版」塚原英治・宮川光治・宮澤節生(編著) 現代人文社 2007年 3月
島田陽一
「今後の労働時間法制のあり方」『労働法律旬報』1641号 16-26頁 2007年 2月 旬報社
「企業組織再編と労働関係―労働法学の立場から」『ジュリスト』1326号 170-175頁 2007年1月 有斐閣
「ホワイトカラー労働者と労基法41条2号」『季刊労働法』214号 30-38頁 2006年9月 労働開発研究会
大塚直
「論点講座環境法の新展開(10)予防原則・予防的アプローチ補論」『法学教室』313号 67-76頁 有斐閣
「論点講座環境法の新展開(11)「持続可能な発展」概念」『法学教室』315号 67-76頁 有斐閣
「環境訴訟における要件事実」大塚直・手塚一郎共著 企画委員代表:伊藤滋夫『要件事実の現在を考える』 2006年 株式会社商事法務
戒能通厚
「司法改革と法律家論-あるアメリカの法律家、民科法律部会」『法の科学』36号(特別増刊号) 2006年 6月 177-183頁 日本評論社
「総論-法整備支援と市場経済化」 共著『法整備支援と市場経済化(土地と利用)科学研究費研究成果報告書』第3巻 7-28頁 2006年 3月 名古屋大学法政国際教育研究センター
「学際的協働を求めて」 共著『法整備支援と市場経済化(土地と利用)科学研究費研究成果報告書別冊』 2006年 6月 1-201頁 名古屋大学法政国際教育研究センター
戸波江二
パネルディスカッション「二一世紀の安全と自由--犯罪の有効な未然防止のための規制の可能性」『警察政策』8号 2006年 警察政策学会
浦川道太郎
「住宅売買において迷惑行為をする隣人の存在を告げなかった売主及び仲介業者の説明義務違反」『私法判例リマークス(法律時報別冊)』33号 4頁 日本評論社
「東大輸血梅毒事件」『医事法判例百選(別冊ジュリスト183号)』 2頁 有斐閣
「使用者責任と共同不法行為責任」 椿寿夫ほか編『関連でみる民法II』 8頁 日本評論社
加藤哲夫
「再建型倒産手続の概要」櫻井孝一ほか編『倒産処理法制の理論と実務』 2006年 18-21頁 経済法令研究会
「破産法」 2006年 弘文堂
「企業倒産処理法制の基本的諸相」 2007年 成文堂
田口守一
「事実認定の多元性」『刑事法ジャーナル』4号 2-9頁 イウス出版
「改正刑訴法と当事者処分権主義」『研修』692号 3-10頁 誌友会研修編集部
「分科会の趣旨 (特集刑事弁護の機能と本質)」『刑法雑誌』44巻3号 351-353頁 日本刑法学会
近江幸治
「日本抵押権実行制度的最新修改」『中日民商法研究』第4巻 153-163頁 北京・法律出版社
「商業性包租契約問題在日本的新動向」『中日民商法研究』第5巻 135~155頁 北京・法律出版社
「物権法」『中国・北京大学出版社』(中国語版)
渡辺宏之(COE専任教授)
「受益権の性質」(道垣内弘人=小野傑=福井修編『新しい信託法の理論と実務(金融・商事判例別冊特集号)』86頁以下 2007年
翻訳(共訳)「日欧シンポジウムヨーロッパと日本 -企業・資本市場・市民社会の現在と未来-」『季刊 企業と法創造』第10号 5頁以下
〔文献紹介・コメント〕「競合する規範と社会的進化:最適な規範は効率的であるか?Paul G. Mahoney and Chris W. Sanchirico , Competing Norms and Social Evolution : Is the Fittest Norm Efficient ? ,149 U. Pa. L. Rev. 1717(2001)」『季刊 企業と法創造』第9号 101頁以下
齊藤直(COE助手)
「株式分割払込制度を背景とした過剰投資-戦間期を対象とした集計データによる検討と樺太工業のケース-」『季刊 企業と法創造』第8号 153-174頁
「書評:清水剛『合併行動と企業の寿命―企業行動への新しいアプローチ』」『経営史学』42-1 経営史学会
「『周回遅れ』の金融コングロマリット:シティバンク×三菱東京UFJ銀行」塩見治人・橘川武郎編『日米企業のグローバル競争戦略』第11章 名古屋大学出版会
張睿瑛(COE助手)
崔成俊、張睿暎(翻訳)「韓国知的財産権関連判例の傾向(1)」 A.I.P.P.I.(月報)51巻9 号 2頁
崔成俊、張睿暎(翻訳)「韓国知的財産権関連判例の傾向(2)」 A.I.P.P.I.(月報)51巻10号 2頁
二本柳誠(RA)
(翻訳)「ローランド・シュミッツ『ヨーロッパにおける資本市場の刑法的保護』」『季刊 企業と法創造』第8号 51-78頁
(論説)「公益通報者保護法と刑法」田口守一=甲斐克則=今井猛嘉=白石賢編『企業犯罪とコンプライアンス・プログラム』 2007年4月 198-218頁 商事法務
川名剛(RA)
「"Financial Cooperation in Asia and Japanese Law, with Particular Reference to the Development of Asian Bond Markets"」『International Corporate Rescue』Vol. 3, Issue 3 (June, 2006)
「多数債権者間の国家債務再構築の法的枠組み-アジア債券市場の展開を契機として-」『日本国際経済法学会年報』第15号 2006年10月
「アジア金融セクターの規制緩和に関する法制度研究」(平成18年度金融庁委託研究)インド担当 2007年 3月 345-373頁
岡部雅人(RA)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条にいう「みだりに」「捨て(る)」の意義」『法律時報』78巻12号 108頁以下
「連邦政府の補助金を受ける州その他の団体の職員への贈賄処罰に関する連邦法の合憲性 Sabri v. United States,
541 U. S. 600(2004)」『比較法学』40巻2号 326頁以下
「企業犯罪の抑止とコンプライアンス・プログラムに関する覚書――ドイツにおけるインタビュー調査の報告――」『季刊 企業と法創造』第9号
手塚一郎(RA)
「環境訴訟における要件事実」大塚直・手塚一郎共著 企画委員代表:伊藤滋夫『要件事実の現在を考える』 株式会社商事法務 2006年
兪風雷(RA)
「中国の知財法の最新動向」『季刊 企業と法創造』第7号
小川明子(RA)
「アメリカにおける追求権保護の可能性」『季刊 企業と法創造』第8号
平成17年度
上村達男
「楽天対TBS 企業買収論議の死角」『世界』747
「市民社会的基盤に立つ企業社会の確立に向けて」『日経研月報』328
「清算関係 (特集新会社法の制定)」『ジュリスト』1295
「論点整理証券市場の本質から見た5視点」『エコノミスト』83(43)
「証券取引所の自主規制機能」『証券アナリストジャーナル』43(7)
高林龍
『標準特許法〈第2版〉』有斐閣
「統合的クレーム解釈論の構築」『知的財産法の理論と現代的課題』(中山先生還暦記念論文集)弘文堂
『不正競争防止法をめぐる実務的課題と理論』青林書院
木棚照一
『開発途上国の経済法制改革とグローバル化』アジア経済研究所
『国際私法概論[第4版] 』有斐閣
『プライマリー国際取引法』法律文化社
宮島洋
「グローバル経済下の日本の社会保障改革」『財政研究:グローバル化と現代財政の課題』有斐閣
“Pension Reform as a Political Football”Japan Echo、32(1)
“Reform of Social Security Swing into Motion”Japan Economic Currents、57
宮島英昭
“Relationship Banking and Debt Choice”Corporate Governance: An International Review、13(3)
「状態依存ガバナンスの進化と変容」伊藤秀史編『リーディングス日本の企業システム2』有斐閣
「M&A何が変わる」『経済セミナー』2005年3月号
加古宜士
「改正公益法人会計基準が目指すもの」『公益法人』34(1)
「新公益法人会計基準の特徴と課題」『企業会計』57(2)
『公益法人会計基準の解説』公益法人協会
内田勝一
「賃借権の承継」『民事法Ⅲ 債権各論』日本評論社
「民法判例レビュー」『判例タイムズ』1166
「都市居住推進手法としての定期借地制度」『都市問題研究』
宮澤節生
「政策志向的現代型訴訟の現状と司法制度改革継続の必要性」『法社会学』63
『法曹の倫理と責任(補訂版)(上)(下)』現代人文社
「今次司法改革における『市民のための司法改革』論の軌跡」『法律時報』77(8)
島田陽一
「情報と労働法」『日本労働法学会誌』105
『ケースブック労働法』有斐閣
『労働法第2版』有斐閣
大塚直
「中長期的な地球温暖化防止の国際制度設計」『季刊環境研究』138
「EUの排出枠取引制度とわが国の課題」『ジュリスト』1296
「京都議定書発効と温暖化対策--特集にあたって」『ジュリスト』1296
戒能通厚
「人権法の適用と「現代的」エクイティの生成」『比較法研究』
「比較法学に関する若干の問題」『比較法研究』66
「横断型基幹科学技術への期待」『日本学術会議・学術の動向』
戸波江二
「被害者の人権のための人権論からのアプローチ」『被害者学研究』15
『憲法ケースブック』日本評論社
「憲法学からみた社会権の権利性」『国際人権』16
浦川道太郎
「日本における法科大学院教育」『全北大学校法科大学シンポジウム報告集』
「スポーツ産業振興のための法的課題:日本」The Journal of Sports and Law、6
「ドイツ法における交通事故慰謝料」『交通法研究』有斐閣
加藤哲夫
「相殺権」『ロースクール倒産法』有斐閣
『破産法〔第4版〕』弘文堂
『総論・破産免責』金融財政事情研究会
田口守一
「刑事弁護の機能と本質・分科会の趣旨」『刑法雑誌』44(3)
「日本的陪審制度-『裁判員』『制度』」『法律活用』2005年第4期
「刑事免責による証言強制-ロッキード事件」『ジュリスト刑事訴訟法判例百選(第8版)』
近江幸治
『民法講義Ⅳ債権総論〔第3版〕』成文堂
『民法講義Ⅲ担保物権〔第2版〕』成文堂
『民法講義Ⅰ民法総則〔第5版〕』成文堂
渡辺宏之(COE専任助教授)
「スコットランドにおける『信託』の法概念」比較法学39巻3号(2006年3月)
「知的財産権の一括管理と信託」知財管理651号(2005年4月)
「企業・市場・市民社会と法律学」『季刊企業と法創造』第4号
村上誠
「インサイダー取引規制に関する経団連提言の検討」『季刊企業と法創造』第4号
齊藤直(COE助手)
「20世紀日本企業の所有構造とパフォーマンス―戦前期を中心にして―」『季刊企業と法創造』第4号
「創業1世紀の軌跡」「地域営業体制の確立」『東京海上百二十五年史』東京海上日動火災保険株式会社
今村哲也(COE助手)
「改正商標法における地域団体商標制度について」知財管理55巻12号(2005年11月)
「タイ王国における知的財産法制度の状況(1)(2)」『季刊企業と法創造』第5・6号
「イギリスにおける同一性保持権と表現の自由に関する一考察」 法研論集117号(2006年6月)
川名剛(RA)
「ソブリン債をめぐる法的課題-アジア債券市場創設に向けての予備的考察-」『季刊企業と法創造』第4号
「電子商取引における国際裁判管轄と経済法の適用」『季刊企業と法創造』第5号
内山敏和(RA)
「現代市民社会と法律行為法-オランダ民法典を視点として-」『季刊企業と法創造』第5号
青柳由香(RA)
「太平洋共同体における地域的フレームワーク及びモデル法による伝統的知識・文化的表現の保護に取組み」
『季刊企業と法創造』第5号
兪風雷(RA)
「中国における企業従事者の発明権利帰属問題」『季刊企業と法創造』第5号
小川明子(RA)
「日本における追求権保護の可能性」『季刊企業と法創造』第6号
張睿瑛(RA)
「近年の米国のデジタル著作権関連法の立法動向」『季刊企業と法創造』第6号
平成16年度
上村達男
取締役・執行役概念の再構成商事法務1710号2004年/市場監視機能・体制の強化ジュリスト1280号2004年/証券市場・株式会社・市民社会TNC政策研究シリーズ1(シンクネットセンター21)2004年
高林龍
書籍(英和対訳 アメリカ著作権法とその実務、雄松堂出版、単行本、2004年 12月、監修)/論文(著作権の制限 著作権関係訴訟法・新裁判実務大系/青林書、22巻、420-432ページ、2004年 12月)・判例研究(平成16(2004)年当初に言渡された職務発明関係判例3件の注目点、判例タイムズ/判例タイムズ社、1146号2004年 6月)
宮島洋
論文【「社会保障の財政制度」、堀勝洋編『社会保障読本(第三版)』所収 東洋経済新報社、2004年3月】/論文【「年金と財政・税制」、年金総合研究センター『年金と経済』第23巻第1号、2004年5月】/論文【「課税と社会保障」、財政学研究会『財政と公共経済』第26巻第2号2004年10月】
宮島英昭
共著【「進展するコーポレートガバナンス改革と日本企業の再生」財務省財務総合研究所『ファイナンシャル・レヴュー』Vol.69、240-277、(原村健二・稲垣健一氏と共著)】/共著【「戦後日本企業の株式所有構造:安定株主の形成と解消」財務省財務総合研究所『ファイナンシャル・レヴュー』Vol.69、278-312、(原村健二・江南喜成氏と共著)】
鎌田薫
論文(知的財産担保融資の現状と課題-法律面からの考察岐阜を考える/(財)岐阜県産業経済振興センター、119巻、2004年 4月)/論文(対抗問題と公示<(財)知的財産研究所『知的財産に関するライセンス契約の適切な保護の調査・研究報告書』所収>、(財)知的財産研究所、2004年 3月)
島田陽一
論文(日本における労働市場・企業組織の変容と労働法の課題、季刊労働法/労働開発研究会、206号2004年 9月)/論文(Working Hour Schemes for White-Collar、Japan Labor Review1;4巻、2004年 9月)
戒能通厚
【「近代法における『共同性』の『発見』」(丹宗暁信・小田中聡樹編『構造批判と法の視点』、2004年6月、花伝社、23-37頁)】/【「『憲法と民法』へのコメントー市民的自由から人権へ?」、法律時報、76巻2号、2004年2月号、82-86頁】
戸波江二
「憲法裁判の発展と日本の違憲審査制の問題点」ドイツ憲法判例研究会編『憲法裁判の国際的発展』(信山社)37-60頁 (2004)/Koji Tonami, Die Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit und die Probleme der richterlichen Prufungsbefugnis uber die Verfassungsmassigkeit in Japan, Christian Starck (Hrsg.), Fortschritte der erfassungsgerichtsbarkeit in der Welt --- Teil Ⅰ, Nomos Verlag 2004, S. 15-33.
加藤哲夫
論文【新破産法における保全処分等、ジュリスト/有斐閣、1273号19頁~26頁2004年 8月)・/共編著・分担執筆【更生債権・共益債権・開始後債権伊藤眞=西岡清一郎=桃尾重明編『新しい会社更生法-モデル事例から学ぶ運用上の論点』有斐閣、2004年 2月)/論文【他の手続の中止命令・包括的禁止命令、判例タイムズ(臨時増刊「新会社更生法の理論と実務)
尾崎安央
「監査役監査基準の改定」月刊監査役491号 34-43頁、492号 42-55頁 (2004)
渡辺宏之(COE専任助教授)
著書:財団法人知的財産研究所編、新井誠=渡辺宏之著『知的財産権の信託』(雄松堂、2004年5月)/著書:『資産流動化対象資産としての知的財産』(財団法人知的財産研究所、2004年3月、単著、英文翻訳付)/論文:ノウハウの現物出資・信託」季刊企業と法創造第2号127-140頁(早稲田大学21世紀COE企業法制と法創造総合研究所、2004年 4月)。/「知財ファイナンスと信託」季刊企業と法創造第3号65-80頁(2004年 11月)。
今村 哲也(COE助手)
高林龍監訳 今村哲也=安藤和宏訳『アメリカ著作権法とその実務』(雄松堂出版、2004年12月)/「日韓自由貿易協定と知的財産法」季刊企業と法創造1巻3号278-288頁(早稲田大学21世紀COE企業法制と法創造総合研究所、2004年 11月)/「著作権法と表現の自由に関する一考察―その規制類型と審査基準について―」季刊企業と法創造1巻3号81-93頁(2004年 11月)/「タイ王国判例調査報告」季刊企業と法創造1巻2号59-63頁(2004年 4月)/今村哲也=鈴木康司「団体商標、証明商標制度における産地表示保護の比較法的考察」(AIPPI49巻8号2-18((社)日本国際知的財産保護協会、2004年 8月)
村上 誠(学術振興会特別研究員、COE書記)
「インサイダー取引規制における「市場」理念の深化」(NIRA(総合研究開発機構)報告書『マーケット・ガバナンス』2005年3月に掲載)
袁藝(RA)
木棚照一監修・袁藝翻訳『中国国際私法模範法』日本加除出版株式会社 2004年7月30日)
川名剛(RA)
論文「多国籍金融機関の法的規律(一)-多国籍企業に対する管轄権の新たな態様としてー」早稲田大学大学院法研論集弟110号、2004年6月、29-56頁。/論文「多国籍金融機関の法的規律(二)-多国籍企業に対する管轄権の新たな態様としてー」早稲田大学大学院法研論集弟111号、2004年9月、79-103頁。
原田和往(RA)
「遡及処罰法禁止条項と出訴期限制度」早稲田法学第79巻第4号(2004年)249頁以下
長谷河亜希子(RA)
「フランチャイズ契約と不公正な取引方法」法学セミナー2004年10月号(598号)40~43頁
|
COPYRIGHT 早稲田大学グローバルCOEプログラム <<企業法制と法創造>>総合研究所 Allrights Reserved. Global COE, Waseda Institute for Corporation Law and Society. |