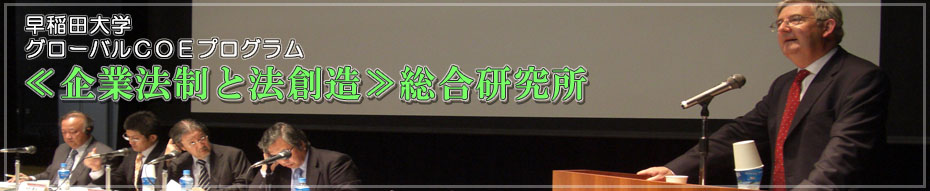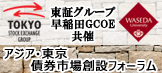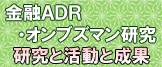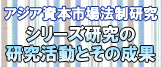| 2010/03/28 |
�m�I���Y�V���|�W�E��
�u���Ɨ��̋��Ԃ���̔��� �|�f�U�C���̖{���Ɩ@�I�ی�̖�����T��|�v |
�y���ԁz13:00�`17:00
�y�ꏊ�z����c��w���ۉ�c���[��L�O�z�[��
�y�T�v�z
�@�킪���̈ӏ����x�́A���傫�ȋȂ���p�ɗ����Ă��܂��B���x�����̐Ⓒ���ɂ�����'80�N�㏉���ɂ͔N��6�����قǂɂ��B�����ӏ��o�肪�A���̌�Q����������N��3�����قǂƂȂ�܂����B����30�N�قǂŏo�萔�������������ƂɂȂ�܂��B�ߎ��̕s���̑��A�������������n�������ʁA�܂��A���i�`�Ԃɑ��鑼�@�̕ی삪������Ȃ������ʁA�����ӏ����x�����S���Ă����͕�i��̖������ɂȂ��Ă��邱�ƂɁA���p�x���ቺ���Ă���傽�錴��������Ɛ�������܂��B
�@���̂悤�ȏ́A���邢�́u�]���̃p���_�C�����ł͍ő��ӏ����x�𗘗p����Ӌ`�͏������v���Ƃ��Ӗ����Ă���̂�������܂���B�܂��A���������f�U�C���͕��ȓI�����Ɨ��ȓI���������n��ł��邱�Ƃ���A���̖@�I�ی������c�_�͂�����̐������������邩�ɋ���傫����X��������A���̂��Ƃ��A�ӏ��@�̐v�Ȃ������߂ɑ傫�ȍ����^���A���x�̐ϋɓI���p�ɑ��鍑���̃��`�x�[�V���������킹�Ă������ʂ����邱�Ƃ��ے�ł��܂���B
�@�������Ȃ���A���̈���ŁA�f�U�C���Ƃ������Y���킪���̎Y�Ƃ������������A�܂��A����ꍑ���̐�����L���ɂ��邽�߂̏d�v�ȃt�@�N�^�[�̈�ł��邱�Ƃ��A�����炭�N���ے肵�Ȃ��ł��傤�B�����ł���Ȃ�A��X�́A���̎��Y���ǂ̂悤�ɕی삷��A����B��������������̂ɍł��L���ł���̂����A���^���ɍl���n�߂�K�v������܂��B
�@����̃V���|�W�E���́A����ꑁ��c��w�d�_�̈挤���@�\�E�m�I���Y���_�`�����������ڎw�������Z���^�����̑ΏۂƂ��āA����u���Ɨ��v�̋��ԂɊׂ����m�I���Y�ł���f�U�C���ɒ��ڂ��A�킪���̍ł������ȃf�U�C�i�[�̂���l�ł�����a�j����w���������}�����Ĉӏ��@���ی삵�悤�Ƃ��Ă���u�f�U�C���v�Ƃ͖{���ǂ̂悤�Ȃ��̂��𖾂炩�ɂ���ƂƂ��ɁA�w�ҁE�s�����E�����Ƃ��\������X�ɓo�d���Ē����p�l���f�B�X�J�b�V�����ɂ����Ĉӏ��@�Ƃ����`���I�Ȑ��x������̂킪���Y�Ƃɏ\���ɓK��������ɂ͂ǂ̂悤�ȕϊv���s����ׂ����A��X�����ׂ����_�͂Ȃ�ł��邩��T��A�ӏ��@���u���Ɨ��v�̋��Ԃ�����Ă����邽�߂̋N�_�ƂȂ邱�Ƃ�ڎw���܂��B
| �y�����i��z | | ���с@���i����c��w�@�w�w�p�@�����j | | | | �y�v���O�����z | 13:00
�`14:30 | ��ꕔ
�@��u���F���a�j�i����w�����j
�@�R�����g�F���с@���i����c��w�����j | | | 14:40
�`17:00 | ���
�@�i��F�基�N��i������w�����j | �@�p�l���X�g�F
�@�c���P�V�i�k�C����w��w�@�@�w�����ȋ����j
�@���F�F�i�������ӏ��ۉے��j
�@���@�B�v�i�ٗ��m�j
�@�ܖ��i�ٗ��m�j |
| | | 17:30�` | ���e��i��G���301-302�j���4000�~ |
�y��Áz
����c��w�m�I���Y���_�`���������iIIIPS Forum�j
�y���Áz
����c��w�O���[�o��COE���Ɩ@���Ɩ@�n������������@�m�I���Y�@�������Z���^�[
�y�ΏہzWeb�ォ��̂��o�^�͒��ߐ�܂����B
|
| 2010/03/20 |
�m�I���Y�V���|�W�E��
�u���Ɨ��@�Λ����狦���ց|�����Z���^�m�I���Y�̊��p���@��T��|�v |
�y���ԁz13:00�`17:20
�y�ꏊ�z����c��w����c�L�����p�X14����201����
�y�T�v�z
�@�����͑�w�⌤���������Ċ�ƂŎY�ݏo����܂����C�ӗ~�������Ĕ�����n�o���C��������������ėL���Ɋ��p���C�m�x�[�V�����������N�����Ă������߂ɂ́C���n�̌����҂�����ƂƖ@���W�̌����҂�����Ƃ̋������K�v�Ȃ��Ƃ͖��炩�ł��B�������C����܂ŁC�@���₻�̎����V�X�e�����Ɋւ��u���v���甭�M�����s���s�����C�u���v���̌n�I�Ɏ~�߂āC���ǂ�����������o���Ƃ̕��̂��邱�Ƃ͏��Ȃ��C���҂͑Λ�����ɗ��܂��Ă�����������܂��B
�@����ɁC�u�����v�̋��Ԃŕ��u����Ă����킪���̉ۑ�̈�ɁC�m�I���Y�@�����l�E���l�E����Ɋ�Â��Ĕ��f���������X�Ɛ�[�������ʂ̊l���ɐ��E�g�b�v���x���ŋ��������Ă��錤������̕��X���O���[�o���Ȏ��_�Ɋ�Â��āu�m�I���Y�@�v�̂���ׂ��p�ɂ��Đ[���c�_�����������Ă��Ȃ��������Ƃ�����܂��B
�@����C��茤���ҁC�|�X�h�N�C��w�@�������C����܂ł̕����̕ǂ��z�������_�ł̋c�_��擱���C�C�m�x�[�V�����n�o�̑��i�Ɍq����u�m�I���Y�@���p�v�̃V�X�e���̍\�z��ڎw���V�����u�l���v�ł���Ɗ��҂���Ă��܂��B
�@�{�V���|�W�E���́C�F�����_�C�I�[�h�̔����҂Ƃ��Ē����Ȓ����C��J���t�H���j�A��w�T���^�o�[�o���Z�����Ɋ�u�����ق��C�u���v�Ɓu���v�̌����ҁE�����Ƃ��\����o���̕��X�ɓo�d���Ē����C����c��w�d�_�̈挤���@�\�E�m�I���Y���_�`���������̃X�^�[�g�A�b�v�Ƃ��āC�u�����Z���^�̒m�I���Y���p���@�v��T�낤�Ƃ�����̂ł��B�p�l���f�B�X�J�b�V�����ł́C�����̘b����c�_���邾���łȂ��C�������S���u�l���v�Ɍ������M�����b�Z�[�W�����M�������܂��B
�y�u���ҁz
�����C��i�J���t�H���j�A��w�T���^�o�[�o���Z�����j
�F�q���j�i�������������@���������ٌ�m�j
����N�\�i����c��w���H�w�p�@�����j
�����i�c��`�m��w��w�@�@�������ȋ����j
�y�i��E�R�����e�[�^�z
���с@���i����c��w�@�w�w�p�@�����j
�����@���i����c��w���H�w�p�@�����j
�y���e�� ���A�z
���䍎�F�i����c��w�����A���H�w�p�@�����j
�y�v���O�����z
| ��ꕔ | | 13:00 | �J��̈��A�i���с@���j | | 13:10 | ��u���F�u���ĂŔ����ҁE�����҂Ƃ��Ċ������āv
�i�����C��j | | 14:00 | �u���Ēm������������S������ٌ�m�̗��ꂩ��v
�i�F�q���j�j | | 14:30 | ���n�����҂���̃R�����g�i���с@���j | | 14:40 | ���n�����҂���̃R�����g�i�����@���j | | 14:50 | �x�e | | | | ��� | | 15:10 | �u�Y�w�����ɂ�錤���J���Ǝ��p���̎���v
�i����N�\�j | | 15:40 | �u�@�w�҂̗��ꂩ��v(����) | | 16:10 | �p�l���f�B�X�J�b�V����
�i��i�s�F�R�[�f�B�l�[�^�[�F���с@���E�����@��
�p�l���X�g�F�����C��E�F�q���j�E����N�\�E���� | | 17:10 | ��̎��F�����@�� | | | | | 17:45 | ���e��i��G���301-303�j���3000�~
���A�F���䍎�F |
�y��Áz
����c��w�m�I���Y���_�`���������iIIIPS Forum�j
�y���Áz
����c��w�O���[�o��COE�@�m�I���Y�@�������Z���^�[(RCLIP)
����c��w�O���[�o��COE �u���H�I���w�m�v
����c��w�i�m�e�N�m���W�[�t�H�[����
����c��w��[�Ȋw�E���N��×Z�������@�\�iASMeW�j
����c��w���m�L�����A�Z���^�[
�y�㉇�z
�h�C�c�w�p�𗬉�iDAAD�GDeutscher Akademischer Austauschdienst�j
����c��w�����w�����ȃW���[�i���Y���R�[�X
�y�ΏہzWeb�ォ��̂��o�^�͒��ߐ�܂����B
|
| 2010/02/26 |
RCLIP��30����u���j�̂Ȃ��̓����|�ߑ�������x�̐v�Ɣ��W�|�v |
�y���ԁz18:30�`20:30
�y�ꏊ�z����c��w����c�L�����p�X8����412����
�y�e�[�}�z���j�̂Ȃ��̓����|�ߑ�������x�̐v�Ɣ��W�|
�y�ҁz�Έ�@���i���H�Ƒ�w��w�@�m�I���Y�����Ȓ��E�����j
�y�v�|�z
���F�l�c�B�A�Ɏn�܂�ߑ�������x�ɂ��āA���̗��j�I���W�ߒ���R���A�����A�i�����Ƃ������_����ڂ������Ă����܂��B�����19���I���̉��B�ɂ����锽�����^������A1873�N�̃E�C�[�����ۓ�����c�ɂ���������i��ւ̓]��A�����ăp�����ւ̌����̉ߒ��ɂ��Ă����Ă������Ƃɂ��A����������x�̉ۑ�����ւ̎Q�l�Ƃ��Ă����܂��B
�y�ΏہzWeb�ォ��̂��o�^�͒��ߐ�܂����B
|
| 2010/01/29 |
RCLIP��29����u�Njy���̐��E�I�g��Ƃ��̔w�i�v |
�y���ԁz18:30�`20:30
�y�ꏊ�z����c��w����c�L�����p�X8����3�K���c��
�y�e�[�}�z�Njy���̐��E�I�g��Ƃ��̔w�i
�y�ҁz���얾�q�i����c��w�@���O���[�o���b�n�d����j
�y�v�|�z
�@�Njy���́A1920�N�Ƀt�����X�őn�݂���Ĉȗ����E�ɍL�����Ă���B2006�N1��1���������Ƃ��āAEU����15�J���i�����j�ɒNjy�����x��ۗL���邱�Ƃ��`���t�����A���̌�AEU�̋K�͂̊g��������āA2009�N����54�J���ւƊg��𑱂��Ă���B�A�t���J�A����Ăł��Â�����Njy�����x�������X�����邪�A�ŋ߂ł́A�C���h�A���B�ɂ��@���x������Ă���B����ŁA�č��ɂ����ẮA�x���k���ւ̉����̍ۂɁA�A�M�@�ւ̒Njy�������̋c�_���s��ꂽ���A�����ɂ́A���������ł���Ƃ��ꂽ�o�܂�����A�ȗ��Njy���̓����ɂ��Ă͌�������Ă��Ȃ��B�B��J���t�H���j�A�B�ɂ́A�B�@�Ƃ��Ă̒Njy��������݂̂ł���B�킪���ł͖��������̌����̘�ɂ����̂ڂ邱�Ƃ͂Ȃ��������A2009�N6��19���̒��쌠�@�̈ꕔ�����ɂ���āA�ɂ킩�ɒ��ڂ��W�ߎn�߂Ă���B
�@�{�ł́A�Njy���ɌW��EU�w�߂��T�ς���ƂƂ��ɁA�킪���ɂ�����Njy�������̉\���ɂ��Č�������B
�y�ΏہzWeb�ォ��̂��o�^�͒��ߐ�܂����B
|
| 2009/12/19 |
JASRAC�A�����J��t�u����6��@�u�t�F�A���[�X�K�������ۑ�ƓW�]�v |
�y���ԁz13:00�`14:30
�y�ꏊ�z����c��w����c�L�����p�X�W����B107����
JASRAC�A�����J��t�u���̏ڍׂ͂�����
�y�i��z
���������i�}�g��w��w�@�r�W�l�X�Ȋw�����ȏy����)
�y�u�t�z
���R�h�m�i�ٌ�m�j
�@�����C���쌠�@����ōł����ڂ���Ă���u�t�F�A���[�X�K��v�̈Ӌ`�Ɖۑ�ɂ��āC���{�ŋK��̂���ׂ��p�̓W�]���܂߂Č�������B
�y�ΏہzWeb�ォ��̂��o�^�͒��ߐ�܂����B
|
| 2009/12/12 |
JASRAC�A�����J��t�u����5��@��JASRAC�|RCLIP�m�I���Y�@�V���|�W�E���� �m���N����5���N�L�O�w�ߎ��̒m�I���Y�@���߂��鏔���x |
�y���ԁz13:00�`17:30
�y�ꏊ�z����c��w����c�L�����p�X�W����B107����
JASRAC�A�����J��t�u���̏ڍׂ͂�����
�p�l���P 13:00�`15:00
�y�e�[�}�z
�|�\�l�̎����E�ё��̖@�I�ی� �\ �p�u���V�e�B���̍ŐV���� �\
�y��Áz
����c��w��w�@�@�������ȁE�@�����猤���Z���^�[
�y���Áz
����c��wGCOE�m�I���Y�@�������Z���^�[�iRCLIP�j
�y���e�z
�@�|�\�l�̎�����ё��̓p�u���V�e�B���ɂ���ĕی삳��Ă���B�����Ƃ��A�킪���ł̓p�u���V�e�B���Ɋւ��閾���̋K�肪�Ȃ����߁A���̕ی�͈́E��́E�q�̂ȂǁA���܂��܂ȉۑ肪�c���ꂽ�܂܂ƂȂ��Ă���B�{�p�l���ł́A�A�����J����уh�C�c�ɂ�����ŋ߂̓����܂��A���_�I����ю����I�Ȋϓ_����킪���ɂ�������ߘ_����ї��@�_��͍�����B
�y�i��z
���B�O�@������w�@�w���y����
�y�p�l���X�g�z
�ɓ��@�^�@�@���������C�I�^�E�ٌ�m
��絍O�i�@�_�ސ��w�o�c�w���y����
�{�R��O�@���m�ڑ�w�@�w���y����
�p�l��2�@15:30�`17:30
�y�e�[�}�z
�����|5�N�Ԃ̒m�I���Y�W����Ɗw���̓����|
�y��Áz
����c��w��w�@�@�������ȁE�@�����猤���Z���^�[
�y���Áz
����c��wGCOE�m�I���Y�@�������Z���^�[�iRCLIP�j
�y���^�z
������Џ����@��
�y���e�z
�@�ʍ�NBL�m���N��I.P. Annual Report����2005�ɔ��s����Ĉȍ~5�N���o�߂����B�����ɂ����锻��w���̓����́C�P�N�Ԃ̔����_�����L�����W���ĉ������������̂ł����āC�m�I���Y�@�W�̑S�̑��𗝉������ŋM�d�Ȃ��̂Ƃ��Ē蒅�����B�{�Z�~�i�[�ł͂��̎��M�҂炪���̑������s�Ȃ��ƂƂ��ɁC�����Ȕ����̑����Ɋ֗^���C���N�ٌ�m�ɓ]�����O���ʈꌳ��������R�����g���B
�y�i��z
�a�J�B�I�@����c��w�@�w������
�y�p�l���X�g�z
�ܖ��@�ٗ��m
�����@���@�M�B��w���u�t
�����N��@������w���R�~���j�P�[�V�����w����C�u�t
�y�R�����e�[�^�z
�O���ʈ�@�ٌ�m�C���m�I���Y�����ٔ�������
�y���e��z�@18:00�`
���F��G�K�[�f���n�E�X�R�K
���F�R�O�O�O�~�i�����@���̂����ӂɂ��j
�y�ΏہzWeb�ォ��̂��o�^�͒��ߐ�܂����B
|
| 2009/11/28 |
JASRAC�A�����J��t�u����4��@JASRAC-RCLIP���ےm�I���Y�@�V���|�W�E���w�t�����X�ɂ�����m�I���Y�ی�̍L����|���̌����Ɛ����\�x |
�y���ԁz13:00�`16:30
�y�ꏊ�z����c��w����c�L�����p�X8����B107����
JASRAC�A�����J��t�u���̏ڍׂ͂�����
�y���e�z
�@�č��̒��쌠�@�ɔ�ׂē��{�l�ɓ���݂̔������B�Ƃ�킯�t�����X�́C�`���I�@���x�Ɋ�Â��Ē����ɒ��쌠�ی�@����|���Ă����B�{�Z�~�i�[�́C���B�����L���m���Ă����ׂ����B�ɂ����钘�쌠�@�Ɋւ���d�v���Ƃ��āC�v���_�N�g�f�U�C�����߂���m�I���Y�@�ɂ��ی�̍L����ƁC�t�ɕی�̍L����ɂ�镾�Q��h�~���邽�߂̒��쌠�𐧌��̂�����̓�����グ�āC�����Ȋw�҂Q�����t�����X���珵�ق��āC���{�y�ѕč��Ɣ�r���Ȃ��猟����������B
�y���A�z
���с@���i����c��w��w�@�@�������ȋ����j
�y�i��z
�|���r�q�i���V���g����w�����C����c��w��w�@�@�������ȋ����j
��c�דy�i��q��w�@�w���y�����j
�y�u���҂ƃe�[�}�z
Yves Reboul�i�X�g���X�u�[����w�����j
�u���쌠�@����ё��̒m�I���Y�@�ɂ��v���_�N�g�f�U�C���̕ی�v
Frederic Pollaud-Dulian�i�p������w�i�\���{���k�j�����j
�u�t�����X�ɂ����钘�쌠�̐����ɂ��āi���j�v
�y�R�����e�[�^�[�z
���{�@�̎��_����
��c�דy�i��q��w�@�w���y�����j
�č��@�̎��_����
�|���r�q
�y��Áz
����c��w��w�@�@�������ȁE�@������Z���^�[
�y���Áz
����c��wGCOE�m�I���Y�@�������Z���^�[�iRCLIP�j
(�����ʖ�L(����))
�y�ΏہzWeb�ォ��̂��o�^�͒��ߐ�܂����B
|
| 2009/10/31 |
JASRAC�A�����J��t�u����3��@�u���쌠�ی�̐^�������|����҂��@���Ƃ̗��ꂩ��v |
�y���ԁz13:00�`14:30
�y�ꏊ�z����c��w����c�L�����p�X�W����B107����
JASRAC�A�����J��t�u���̏ڍׂ͂�����
�y�i��z
�x���p���i�ٌ�m�C����c��w��w�@�@�������ȋq�������j
�y�u�t�z
�����@���i�ٌ�m�C�|�p�@����C���l�j
�@���N�ɂ킽��ٌ�m�E��ƂƂ��Ē��쌠�@�ɐ[���֗^����Ă����������ٌ�m�ɁC�{�����쌠�@�����ׂ����͉̂��Ȃ̂���L�x�Ȍo���Ǝ����ʂ��Č���Ē����B
�y�ΏہzWeb�ォ��̂��o�^�͒��ߐ�܂����B
|
| 2009/10/17 |
JASRAC�A�����J��t�u����2��@�u���쌠�ƃR���e���c���ʁv |
�y���ԁz13:00�`14:30
�y�ꏊ�z����c��w����c�L�����p�X�W����B107����
JASRAC�A�����J��t�u���̏ڍׂ͂�����
�y�i��z
�O�c�N�j�i�ٌ�m�C����c��w��w�@�@�������ȍu�t�j
�y�u�t�z
�V���_�M�i�ٌ�m�C�u�l�b�g���[�N���ʂƒ��쌠���x���c��v�R���e���c�̗��ʑ��i����Ɋւ��镪�ȉ��j
�@���앨�̗��ʑ��i�ƌ����ҕی�̃o�����X�́A�ǂ̂悤�ɂƂ�ׂ����H�@���̖��Ɏ��g�ދ��c��ł�������V���ٌ�m�Ɍ���Ē����B
�y�ΏہzWeb�ォ��̂��o�^�͒��ߐ�܂����B
|
| 2009/10/05 |
���ےm�I���Y�Z�~�i�[�u�����V�����@�̉^�p�Ƃ��̓W�]�v |
�y���ԁz18:00�`20:00
�y�ꏊ�z����c��w�Q�P���ّ�G�u���n���P�K�u��G���u���v
�y���e�z
�@���悢��8�N�Ԃ�̑�������o�������V�����@��10��1���Ɏ{�s�����B����܂ł̉�����TRIPs���蓙�̍��ۏ��̗v���ɂ��I�ȉ����ł������̂ɑ��A����̉����͌o�ς̍������W�ɔ����m�I���Y�̏d�v�����F�����ꂽ���ʂƂ��Ă̔\���I�ȉ����Ƃ�������B
����̓����@�����́u�v�V�^���Ƃ̌��݂����A����n�V�\�͂����߂�v��ڕW�Ƃ��A�Ǝ��Z�p�̊J�����i�A�s���y�юi�@�ی�̕⋭�A�������҂̗��v�ƌ��O�̗��v�Ƃ̒��a�A�m�����x�̍��ۋ����ւ̑Ή���ȂǁA����ɂ킽�蒆���̓������x�����V������̂����荞�܂�Ă���A���������֗^����e���͌v��m��Ȃ��B
�{�Z�~�i�[�ł́A�V�����@�̎��{�㒆���ŋZ�p�J��������i�߂Ă�����{��ƂƂ��Ēm���Ă����ׂ����ӓ_�A�V�����@���{��̉^�p�ɏœ_�����킹�A��������A�����@�y�ю��{���̉����ɒ��ڌg��������ƒm���Y���ǂ̐��Ƃ⒆�����\�����w�����A�����Ƃ��R�����ق��āA�����ɂǂ̂悤�ȉe����^����̂���������Ă��������B
�y���A�z
�x�������i����c��w�������E�����o�ϊw�p�@�����j
�㑺�B�j�i����c��w�@�w�w�p�@���E�O���[�o��COE�v���O�������Ɩ@���Ɩ@�n��������������_���[�_�[
�y�R�[�f�B�l�[�^�[�z
���ї��@�i����c��w��w�@�@�������ȋ����E�m�I���Y���@�������Z���^�[���j�@
�y�i��z
�`�����@�i����c��w�O���[�o���b�n�d�������j
�y�ҁz
�P�A�u�V�����@�^�p��̒��ӓ_�v�����̌����͈͂���ѐR���
�@�@���z��@�i���ƒm���Y���Ǔ����Ǖ��i���j
�Q�A�u�V�����@�y�ю��{��������̓W�]�v���������R�قƐ�s�Z�p
�@�@���@���@�i�k����w�@�w�@�����j
�R�A�u�V�����@���{��̎����ɑ���e���v�������s�g�ƐN�Q��
�@�@��?�ǁ@�i��C��w�m���Y���w�@�@���E�ٌ�m�E�ٗ��m�j
�@�@�����i�V��w���@�w�@�@���E�����j
�y���e��z
20:00�`
��G�K�[�f���n�E�X�@2�K
���4,000�~
�y��Áz����c��w���ێY�w���A�g�{��
�y���Áz�O���[�o��COE�s��Ɩ@���Ɩ@�n���t�����������@����c��w�m�I���Y�@�������Z���^�[�iRCLIP�j
(�����ʖ�L(���{��E������))
�y�ΏہzWeb�ォ��̂��o�^�͒��ߐ�܂����B
|
| 2009/10/03 |
JASRAC�A�����J��t�u����1��@�u���쌠�N�Q�i�ׂ̎�����̖��_�v |
�y���ԁz13:00�`14:30
�y�ꏊ�z����c��w����c�L�����p�X�W����B107����
JASRAC�A�����J��t�u���̏ڍׂ͂�����
�y�i��z
���ї��i����c��w��w�@�@�������ȋ����j
�y�u�t�z
�O���ʈ�i�ٌ�m�C���m�I���Y�����ٔ��������j
�@�m���W�̒����Ȕ���ɑ����֗^����C�ߍ��ފ�����ĕٌ�m�ɓ]�����O�������������}�����āA���쌠�W�i�ׂ̎����ɂ��Č���Ē����B
�y�ΏہzWeb�ォ��̂��o�^�͒��ߐ�܂����B
|
| 2009/09/22 |
�����i�אV�����ۃV���|�W�E�� |
�y���ԁz
�y�ꏊ�z��p�@�q�d���Y�@�@
�y�e�[�}�z
���{�ɂ�����R������ѐR������i�ׂƐN�Q�i�ׂ̐R�����f���߂��鏔���
�y�u�t�z
���ї��i����c��w��w�@�@�������ȋ����j
�y�T�v�z
9��22���ɑ�p�������A��p��w���Áu�����i�אV�����ۃV���|�W�E���v���J�Â���C���ٍu�t�Ƃ��č��ї��������u���{�ɂ�����R������ѐR������i�ׂƐN�Q�i�ׂ̐R�����f���߂��鏔���v�Ƒ肵�ču�����s�����B
�܂��A23����p�ō��@�@�A��@�@�̑��c���ŊJ�Â��ꂽ�u�ٗʏ㍐���x��ō��ٔ���̍S�����ɂ��āv�ɂ����č��ї��������u�����s�����B���̖͗l�͑�p�̐V���ɑ�ύD�]�ł������ƌf�ڂ���Ă���B
9��22���̃V���|�W�E���ɂ��Ắc�wRCLIP�j���[�X���^�[��22���x�i�ߓ��f�ځj�̋L�����Q�ƁB
9��23���͓����͍ō��@�@�y�ђq�d���Y�@�@��K�₷�邾���̗\�肪�C�ō��@�@�ł͐���ɂƂ̗v�]�ɂ��A
�ō��ٔ����₻�̑��̔�������100�����Q�������@�@�̑��c���ŗk�@���i�ō��ْ����j�i��̉��ŁC���ї��������ٗʏ㍐���x��ō��ٔ���̍S�����ɂ���90���߂��u���Ǝ��^�������s�����B
�f�ڂ��ꂽ��p�̃j���[�X��
SINA�l�b�g�F�j���[�X
�q�d���Y�@�@�F�g�o�L���i�ʐ^�j
�y���Áz
��p�������@��p��w
�y�Ώہz�Ώۂ́A�����������Q���҂݂̂ł��B
|
| 2009/09/07 |
��RCLIP���B�s�k�n�Z�~�i�[�� �u���B��v�����̋Z�p�ړ]���x�y�тd�t�哱�̋Z�p�ړ]�������㐭��v |
�y���ԁz18:00�`20:00
�y�ꏊ�z����c��w��G�^���[�n����K���ړI�u�`���i����c�L�����p�X�Q�U���فj
�y�R�[�f�B�l�[�^�[�z
���с@���i����c��w�@�w���E�@�������ȋ����j
�y�i��z
���@�͝�i�����s�s��w��C�u�t�j
�y�u �� �ҁz
Luca Escoffier�i���V���g����w���[�X�N�[���q���u�t�A(��)�m�I���Y���������ւ��������j
���� �� �i����c��w��i���H�w�� �����j
�ѓc�������@�i������Ȏ��ȑ�w�@�m�I���Y�{���@���C�����j
�y�v�|�z
�@���B��v�����̋Z�p�ړ]���x�͓��{�ł͗]��m���Ă��Ȃ��B����̃Z�~�i�[�ł́C���ۂɃC�^���A�̃o�C�I�֘A�����Z���^�[�̋Z�p�ړ]�}�l�[�W���[�Ƃ��ē����Ă����o��������Luca Escoffier�������}�����āC�Ƃ�킯���B�ɂ����钆����ƂƂ̘A�g�ɂ��ĐG�ꂽ��C�ŋ߉��B�ψ���u�Z�p�ړ]�����ɂ�����m�I���Y�Ǘ��Ɋւ��銩���v���тɁu��w�y�т��̑��̌��������@�ւ̂��߂̎��{��v�Ƌ��ɍ̑������u�m�I���Y�Ǘ��v��āv�����Љ���C����̒m�I���Y����(IP����)�C�⊮�I�m���ړ]����(KT����)�y�ы��������E�_��x�[�X�����̌����ȂNJe�X�̌����ɂ��Ă̕��͂����Ē������Ƃɂ��Ă���B
�@���̌�ɁC��������������C�u���ۘA�g�̏����t�F�[�Y�ɑ�Ȃ��Ɓ`�{����wLIMES�Ƒ���c��wASMeW�Ƃ̍��ۘA�g������Ƃ��ā`�v�Ƃ̃e�[�}�ő���c�̊��������Љ���C�������ѓc��������������u������Ȏ��ȑ�w�̍��ێY�w�A�g�����̏Љ�`���ċZ�p�ړ]�@�ւƂ̎��g�݂ɂ��āv�Ƃ����e�[�}�œ�����Ȏ��ȑ�w�̊��������Љ���B
�y��Áz����c��w���ێY�w���A�g�{��
�y���Áz���Ɩ@���Ɩ@�n������������@�m�I���Y�@�������Z���^�[�iRCLIP�j
(�����ʖ�L(���{��E�p��))
�y�ΏہzWeb�ォ��̂��o�^�͒��ߐ�܂����B
|
| 2009/07/17 |
RCLIP��28����u�X�y�A�p�[�c�̈ӏ��ی�ɑ��錠�������̉\���Ƃ��̑Ó����\��Ƃ��ĕč��ɂ�����c�_�̏Ƃ��̓��e�𒆐S�Ɂ\�v |
�y���ԁz18:30�`20:30
�y�ꏊ�z����c��w����c�L�����p�X8����3�K���c��
�y�e�[�}�z
�X�y�A�p�[�c�̈ӏ��ی�ɑ��錠�������̉\���Ƃ��̑Ó���
�\��Ƃ��ĕč��ɂ�����c�_�̏Ƃ��̓��e�𒆐S�Ɂ\
�y�ҁz
�����N��i������w���R�~���j�P�[�V�����w����C�u�t�j
�y�v�|�z
�@�X�y�A�p�[�c�̈ӏ��ی�̐����ɂ��ẮA����̐�s�I�ȕ����ɂ�鉢�B�ł̋c�_�̏Љ�������āA�킪���ł͎����̉ۑ�Ƃ��Ă��܂�c�_����Ă͂��Ȃ������B�������A���B���x���ł̃X�y�A�p�[�c�����̓����̓����i�u�ӏ��̖@�I�ی�Ɋւ���1998�N10��13���̉��B�c��y�ї�����w�߁i98/71/EC�j�v�̉����̓����j�ɔ����āA���̖��Ɋւ��鍑���O�ł̋c�_�����܂��Ă��邱�Ƃ��\�z����A���B�ȊO�̏��O���̓����i���ɕč��j�̂�����ɂ���ẮA�X�y�A�p�[�c�ɂ��܂��܂Ȍ��������킪���̎����ԎY�Ƃɑ��Ă��e����^�����˂Ȃ������I�ȉۑ�ƂȂ��Ă���ł��낤�B���̕ł́A��Ƃ��ĕč��ɂ�����c�_�̏Ƃ��̓��e�𒆐S�ɁA�w��ł̋c�_�̏i�{�N�x�̍H�Ə��L���@�w��ɂ����郏�[�N�V���b�v�ł́A�����b����������ії���q�ٌ�m����̂����\�肳��Ă���j�����܂��A���̖��ɂ��ăA�v���[�`����\��ł���B
�y�ΏہzWeb�ォ��̂��o�^�͒��ߐ�܂����B
|
| 2009/06/26 |
RCLIP���ےm���헪�Z�~�i�[�u���ē�������̍ŐV�����v |
�y���ԁz17:30�`19:50
�y�ꏊ�z����c��w��c�L�����p�X����L�O�u��(27���ْn��2�K)
�y�e�[�}�z
���ē�������̍ŐV�����F�r���X�L�E�V�[�Q�[�gCAFC�����Ɋ�Â������헪
�y�v�|�z
�A�����J�ł́A�ŋ߁ACAFC���]���̔���@��傫���ύX�����@�씻�����o���A�����o��y�ь����s�g�����ɑ傫�ȉe����^���Ă���B���Ƀr���X�L�����́A�V���ȕی�K�i����̗̍p�ɂ���āA�r�W�l�X���@�E�\�t�g�E�F�A�֘A�����ɂ��āA�o��l�́A�]���Ƃ͈قȂ�N���[���쐬���H�v���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ����B���B�ł��A���B�������g��R�������A�����̔����̐V���Ȋ��͍����ł���B�܂��A�V�[�Q�[�g�������A�V���Ȍ̈ӐN�Q�̊�̗̍p�ɂ��A��^�N�Q�҂́A�č��ٌ�m�ɊӒ菑���˗�����^�C�~���O���čl����K�v�ɔ����Ă���B�{�Z�~�i�[�ł́A�č��y�щ��B��������Ŋ�������Ƃ����ق��A����画��@�̓������Љ�Ă��炤�Ƌ��ɂ���画�����{�@�Ɣ�r�@�I�Ɍ������A�����s�g���݂����������擾�����y�ѐN�Q�i�זh��헪�ɂ��ču�����Ă��炤�B
�y���Áz
����c��w���ێY�w���A�g�{��
| 17:30 | �J��̎��@�����i��@���ї��@����c��w�@�@�w���@��w�@�@�������ȁ@���� | | 17:40 | ��ꕔ�F�r�W�l�X���@�E�\�t�g�E�F�A�֘A�����̓����ی� | | | �i��F�|���r�q�@�@���V���g����w���[�X�N�[�� | | | �u���� | | | �č��FDoug Stewart���ADorsey&Whitney,Seattle Office | | | ���B�FMatthias Bosch���@Bosch Jehle,Munich,Germany | | 18:30 | �p�l���f�B�X�J�b�V�����F��r�@�I�����y�ю����헪 | | 18:45 | ���^���� | | 19:00 | ��F�V�[�Q�[�g������̓����N�Q�Ӓ菑���� | | | �i��F�|���r�q�@�@���V���g����w���[�X�N�[�� | | | �u���� | | | Paul Meiklejohn���ADorsey&Whitney,Seattle Office | | 19:30 | �R�����g�FMatthias Bosch���@Bosch Jehle,Munich,Germany | | 19:40 | ���^���� | | 19:50 | ��̎� | | 20:00 | ���e��(�`22:00�@���4000�~)
���F�C���E�f�E�p�� |
���́F�i���j�T�C�}���E�C���^�[�i�V���i��
(�����ʖ�L(���{��E�p��))
�y�ΏہzWeb�ォ��̂��o�^�͒��ߐ�܂����B
|
| 2009/06/16 |
RCLIP������u��p�����㍐�����̏������߂��鏔���v |
�y���ԁz14:00�`16:00
�y�ꏊ�z����c��w����c�L�����p�X8����219����c��
�y�e�[�}�z
��p�����㍐�����̏������߂��鏔���
�y�ҁz
������ ��p�ō��ٔ����iPresiding Justice, Mr. Liu, Yen-Tsun�j
薕x�}�@��p�ō��ٔ����iJustice, Ms.Jen�CFu-Chih �j
���`沁@��p�ō��ٔ����iJustice, Mr.Huang, Yih-Feng �j
������ ��p���ٔ����C�ō��ٙ����iJustice, Mr. Hsu, Chen-Shun�j
�y����z
���������i����c��w��w�@�@�������ȁ@�����j
�����E���i����c��w��w�@�@�������ȁ@�q�������j
�y�i�@��z
���с@���i����c��w��w�@�@�������ȁ@�����j
�y�v�|�z
��p�̍ō��ٔ���3���ƍ��ٔ���1���̂S���ɂ��z�����������A��p�̖����㍐�����̏������߂��鏔�����͂��߁A��p�ō��ٔ����̌����ɂ��ču�����Ă��������B
�y�Ώہz�Ώۂ́A�����������Q���҂݂̂ł��B
|
| 2009/05/09 |
RCLIP���ےm���헪�Z�~�i�[�u���{��ƂƓ����i�ׁF�t�H�[�����V���b�s���O�ɂ��U���I�����헪�v |
�y���ԁz13:30�`17:20
�y�ꏊ�z����c��w����c�L�����p�X����L�O�u���i�@�������Ȓn���Q�K�j
�y�e�[�}�z�u���{��ƂƓ����i�ׁF�t�H�[�����V���b�s���O�ɂ��U���I�����헪�v
�y�v�|�z
�p�e���g�g���[���̉��s��Z�p�W���Ɋւ�������̈����Ȍ����s�g���A���{��Ƃ����ێs��œ��������ɂ܂����܂�郊�X�N�͓��X���債�Ă��܂��B������L���ɉ������邽�߂ɂ́A���{��Ƃ��A���̂悤�ȃ��X�N�����������@�m���A�ł��L���ȍٔ����ői�ׂ��J�n���邱�ƌ��ƂȂ�܂��B�{�Z�~�i�[��ꕔ�ł́A�č��@���G���ʼn��x���g�b�v�����i�׃G�L�X�p�[�g�ƑI��Ă���t�B�l�K�����������Ǝ��̃l�b�g���[�N�ŏW�߂��������҂̏��i���E���Q�����z�E�ٌ�m��p���̓��v�f�[�^�Ɋ�Â��A���������ٌ̕�m���������ҁE��^�N�Q�҂ɗL���ȕč��A�M�ٔ����ɂ�����t�H�[�����V���b�s���O�헪�ɂ��ču�����܂��B�X�ɑ�ł́A���̃l�b�g���[�N�ɎQ��������{�E�����E�p���ٌ�m�����B�A�W�A�̎�v�ٔ����ɂ����铝�v�Ɋ�Â��A�t�H�[�����V���b�s���O�헪���u�����A�i�ׂƘa�����̃R�[�f�B�l�[�V�������A���H�I����ɂ��ăp�l���f�B�X�J�b�V������ʂ��Č������Ă����܂��B
�y�e�[�}�y�эu���ҁz
| 13:30 | �J��̎��@�����i��@���ї��@����c��w�@�@�w���@��w�@�@�������ȁ@���� | | | ���A �㑺�B�j�@����c��w�@�w�w�p�@��
GCOE�s��Ɩ@���Ɩ@�n���t�������������_���[�_�[ | | 13:40 | ��ꕔ�F�č��A�M�ٔ����ɂ�����t�H�[�����V���b�s���O�헪 | | | �u���� | | | John Livingstone���AFinnegan Henderson, Tokyo Office | | 14:30 | ���^���� | | 14:45 | �x�e | | 15:00 | ��F���B�A�W�A��v���ٔ����ɂ�����t�H�[�����V���b�s���O | | | �i��F�|���r�q�@���V���g����w���[�X�N�[������ | | | �p�l���X�g�F | | | Xiaoguang Cui���A Sanyou law firm, Beijing | | | ���c�^�ꎁ�A���q�E�⏼�@�������� | | | Richard Price��, Taylor Wessing, London Office | | | John Livingstone���AFinnegan Henderson, Tokyo Office | | 16:30 | ���_ | | 17:00 | ���^���� | | 17:15 | ��̎� | | 18:00 | ���e��:�u���k�̕��v�i��G�^���[�j���4000�~ |
�y�ΏہzWeb�ォ��̂��o�^�͒��ߐ�܂����B
|
| 2009/04/13 |
RCLIP��27����u���ꂩ��̓������Ԃ̐R�����͂Ɗ�Ƃ̍��ۓ����헪�v |
�y���ԁz18:30�`20:30
�y�ꏊ�z����c��w����c�L�����p�X�W���قR�K��c��
�y�e�[�}�z�u���ꂩ��̓������Ԃ̐R�����͂Ɗ�Ƃ̍��ۓ����헪�v
�y�ҁz���q���j�i�ٗ��m�E��ē��������������j
�y�v�|�z
�@���E�e���̒m�I���Y���x�́A�K�ȕی샌�x���Œ��a���Ă��邱�Ƃ��]�܂����B���̂��߂ɂ́A�e���̍����@���K�����鍑�ۖ@�̐��肪�K�v�ł���\�\�B���������l���ɗ����āA���ĉ��́A1980�N��㔼����}���`�̏��Â����i�߁A���̓w�͂́ATRIPS����A�����@���A���쌠���Ɋւ���V���Ƃ��Č��������B
�@�Ƃ��낪�A����Ȃ��ƂɁA�m�����x�̏d�v�����e���ɂ���ċ����F�����������قǁA�}���`�̏����́A�O�ɐi�߂�̂�����Ȃ��Ă����B���̓����@�����́A�����P����Ԃɂ���B���̈���A�O�������̎擾�R�X�g�A�������̏o��؉݁A�s�����i���ɂ�鑹�Q�A�i�׃��X�N�ȂǁA�������ׂ����ۖ��͂�����Ƃ��đ����B
�@���̂悤�ȏ��ɂ����āA�ߔN�A��v���ł́A�ԁE�������Ԃ̑��ݗ��v����Ƃ���������́i�R�����ʂ̌������j�̐��i�A����ь��s�@��O��Ƃ���G���t�H�[�X�����g�i�ٔ��A���ۓ��j�̏[���Ɍ��������g�݂����������Ă���B
�@�{�ł́A��������𒆐S�ɁA���������ŋ߂̓������T�ς��A�킪���Ƃ��ăo�C�E�v�����E�}���`�̌����ǂ̂悤�Ƀn���h�����O���Ă����̂������̂��l����B�܂��A�V���������R�����̓X�L�[�����ɂ�����o��l�̍��ۓ����헪�̑��l���ɂ��Ă��l����B
�y�ΏہzWeb�ォ��̂��o�^�͒��ߐ�܂����B
|