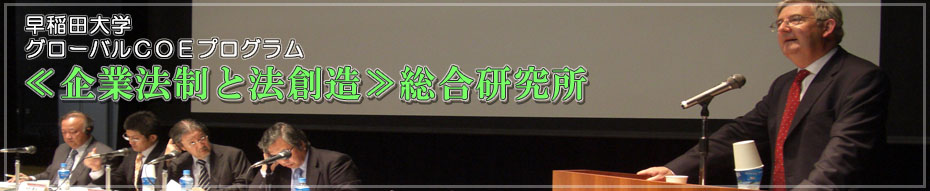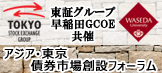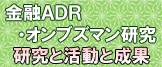|
|
|
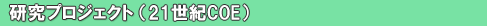 |
各プロジェクトの「研究活動」ボタンをクリックして頂きますと、プロジェクトの議事録や進捗状況などがご確認頂けます。
※各研究企画にはそれぞれ多くの学内、学外研究員が参加しています。 公表可能な部分から公表する予定です。
※各研究企画に登録されている研究員は、特に内部研究者のみとされている企画を除き、 すべての研究会に参加する自由があります。 ただし、開催場所の都合等の関係で、不可能な場合もあるため、研究員が他企画の研究会に参加する場合には、 事前に事務担当者に通知してその了解を得る必要があります。
|
| I-A. 「企業と社会」基礎研究(基礎法・公法部門統括) |
企業の置かれている社会状況と企業活動に対する社会の評価・イメージについて基礎的研究を行い、 もって企業の活動のあり方と社会との関わりについて提言を行う。
企業制度を成り立たせている思想的、公法的基盤について幅広く研究する。 啓蒙思想・市民革命と結社の自由・団体観、企業社会のあり方と市民社会のあり方との関係、 法人の人権論等々、民事法・企業法・資本市場法との共同研究を行う。 |
 |
| ◆ 戸波江二教授 |
| ■ 武田芳樹 |

| I-b. 「基本的法概念のクリティーク」 |
| 日本の企業社会の構造の解明には、 ヨーロッパを出自とする近代法の諸カテゴリーが、 現代日本社会でいかなる変容を蒙りながら理解され用いられているのかを明らかにする必要があろう。 基本的な法概念が形成された思想史的背景に立ち返って概念を位置づけることが本グループの第一の課題である。 また「法の創造」の課題に関しては、いわばフィクションとして構成された近代法の諸基本概念が、 フィクションとしてもつその意義と限界を考察する作業が不可欠といえよう。 「基本的法概念のクリティーク」と題する本共同研究は、 実定法学と基礎法学との新しい協同関係を構築しつつ、新しい法学の可能性を切り開こうとするものである。 その内容は、一言で表現するならば、主要実定法領域における基本的な諸概念をとりあげ、そのexplicatio =Auslegung(解釈)、 つまりサヴィニーが規定した二つの条件の下で解明することである。 それは第一に、個々の法概念や法律条文の背後にある思想、 その思想を生成させた精神活動を生き生きと思い浮かべることであり、 第二に、そのような個々の法概念・法律条文・思想・精神活動なるものを、 個別的なものがそこから光を受けとるところの、法の全体像の中に位置づけること、である。 そのためには、実定法学者と基礎法学者の共同研究も実施しており、一定の成果が上がっている。 |
 |
| ◆ 楜沢能生教授 |
| ■ 上地一郎 |

| I-c. 企業行動の法的・非法的要因に関する実証的研究 |
| アメリカ的市場万能主義が日本で批判されることがあるが、 アメリカ的資本市場ないし株式会社制度を成り立たせている思想的・制度的条件について研究し、 アメリカ法導入の際の方法的視点を確立する。たとえば、おとり操作、盗聴、覆面捜査、SEC、報奨金、司法取引、 クラスアクション、ディスカバリー、そして経済学者も最終的に依拠する連邦最高裁の権威等々、 さらには銃で守ろうとする個人の生活とそこから派生する自己責任原則の意義等、 アメリカにあって日本にない条件を探求することで、真のアメリカ法研究を模索する。また、アメリカにおける法曹の役割についても意義のある研究を行ってい る。 |
 |
| ◆ 宮澤節生教授 |
| ■ 金セイ |

| I-d. 企業と市場の相互作用に関する法学的研究 |
| 本企画は「市場」や「企業」の憲法学的検討を行うとともに、これを踏まえて「市場」の基本的ルールを定める独占禁止法といわゆる領域特定規制を定める事 業法との関係や両者の運用に関して欧米諸国との比較検討を行うなど、さまざまな課題に取り組んできた。2005年5月には2年間の研究を踏まえて、中間報 告書「政府規制と独占禁止法」を取りまとめるなど、着実な成果を上げつつある。 |
 |
| ◆ 須網隆夫教授 土田和博教授 |
| ■ 青柳由香 |
 ▲ページのTOPへ ▲ページのTOPへ
| II-A. 企業と市場に係る民事法総合研究 |
| 従来民事法とりわけ民法は市民法型ルールの提供を第一の使命としてきた。 もとよりその使命の重要性は今後とも揺ぐものではない。 しかし他方で企業ないし市場を支えるような商事的民事法のあり方が真剣に探求されなければならない状況となっている。 市場と不法行為、市場に対する責務の不履行、金融商品の説明義務・適合性原則、市場を経由する消費者・投資家損害の賠償、 金融商品設計に係る民事法の意義、商事信託法制、受託者責任、市場取引の客体たるモノとしての権利、 財団・法人・中間法人・組合といった事業の受け皿法制等々の研究は、主として民法学者に委ねられてきたが、 そこで生じている現象は企業・市場を担い支える民事法という視点を必要とする場合が多い。 本企画はこうした総合分野を共同研究することによって、新たな学問的地平を切り開こうとするものである。 |
 |
| ◆ 鎌田薫教授 上村達男教授 内田勝一教授 浦川道太郎教授 |
| ■ 柴原宏昭 |

| II-b. 企業社会の変容と民事責任システムの新たな構築 |
| 規制緩和時代における民事責任のあり方について、民事責任の原理、救済手段の多様性、 刑事責任ないし行政的規制との関係、法政策の実現と民事責任の役割など、多様な視点から検討し、 企業社会における民事責任像の構築を目指す。本研究は若手研究者の育成をも目的とするものである。全国から研究者が集い、着実な成果が上がっている。 |
 |
| ◆ 藤岡康宏教授 上村達男教授 後藤巻則教授 |
| ■ 谷本陽一 内山敏和 |

| II-c. 日韓中(日中韓)によるアジア民商事法制研究グループ |
アジア各国の法律(私法)は,19世紀に開花したヨーロッパ大陸法の影響を強く受け,その法体系を継受した。 しかし,アジアといっても,国によって独自の文化を持ち,それが多彩な形で法律関係に影響を与えている。 このため,統一的な規範というものを考えることができなかった。 しかし,21世紀の「アジアの時代」において,経済的ないし文化的交流が活発化していることに伴って, 取引法に関する統一的規範の形成は,今や喫緊の課題となっている。 そこで,これまで,日韓間・日中間において培ってきた学術交流の関係を基盤として, 新たに3国間の民商事法制に関する「アジア法研究拠点」を形成し、 「アジア取引法の統一的規範と統一的解釈の可能性」を探ることを目的とする。
また、企業と市場に係る総合法領域が一体となって研究活動を行うことは、 これから本格的に企業と市場に潜む諸問題に直面するであろうアジア諸国にとって、 もっとも有益な知見を提供しうるように思われる。本企画はこうした視点から、 企業・市場法制に関して、日中韓の各国との間に学問交流を活発化させている。 |
 |
| ◆ 田山輝明教授 上村達男教授 近江幸治教授 |
| ■ 青木則幸 大沢慎太郎 |

| II-d. 環境法における予防原則と企業活動 |
今日、日本のみならず諸外国においても、企業活動に環境配慮が求められており、 そのための様々な法制度による規制等が実施されているが、環境の観点から鑑みるとまだまだ十分なものとはいえない。 また、環境に関する法制度については動きが早く、例えばEUでは毎年多くの新しい指令が制定されたり、既存の指令の改正が行われている。
当研究においては、世界の法制度、とりわけEU、アメリカの法制度や、種々の国際条約を素材としつつ、 特に近時注目の的となっている「予防原則・予防的アプローチ」、及び、「リスク論」を中心とした検討を進め、 国際条約及び各国の法制度における化学物質、気候変動、自然保護、遺伝子改変生物等といった各分野での予防原則、 予防的アプローチの適用状況、及び、リスク論を整理している。 |
 |
| ◆ 大塚直教授 |
| ■ 手塚一郎 福田矩美子 |
 ▲ページのTOPへ ▲ページのTOPへ
| III-A. 企業・資本市場法総合研究グループ |
| 日本の金融・資本市場法制のあり方を総合的に研究する中核的な研究グループであり、 他の企画で吸収できない問題を総合的に扱う。 もとより企業資本市場法制関係の各論的な研究グループと一体となって研究を推進する。 ここでは金融審議会等での議論を検証し、場合により対案を提示する。重要なパブリックコメントに応える。 万事、政府からの諮問を受けないと審議できない現状を乗り越える努力を行い、 たとえば金融法制を横断的・包括的に再構成する日本版金融サービス市場法の提案、 その他の制度改革提案のための研究を行う。横断的法制研究については、 現在総合研究開発機構(NIRA)との共同研究が進行中である。 また、日本取締役協会の公開企業法委員会における公開株式会社法要綱案作りに本COEの若手研究者がすでに参画している。 その他、頻繁に行われる会社法改正に対する評価、判例分析、海外法制研究等を実施する。 欧米の企業・市場に関する調査研究グループとの共同研究が実施している。中国全人代法制工作委員会との研究協定の覚書、中国証券管理監督委員会と東証との 三者による研究交流覚書の締結が予定されており、中国における会社法・証券取引法改正に多大な貢献を行ってきている。 |
 |
| ◆ 上村達男教授 正井章筰教授 渡辺宏之准教授 |
| ■ 清水真人 金賢仙 呉棋 金セイ 熊潔 桜沢隆哉 川名剛 |

| III-b. 会社法解釈等総点検研究会 |
| 金庫株の取得、ストック・オプション、種類株式等々、 従来は弊害防止のために原則禁止の立場がとられていた多くの問題が原則自由に転換されている。 会社法の解釈も判例の評価も自由化時代のものに大きく転換される必要がある。 また、閉鎖会社を念頭におかれた戦後判例も、公開株式会社に適用可能か、すべて再吟味が必要である。 まさに法解釈のあり方等につき、鼎の軽重が問われる状況にある。 日本では失敗を経験する前に、予防法学的見地から法解釈論をあらかじめ展開しておくことの重要性が極めて高い。 こうした観点から、会社法解釈、判例の評価、立法提案に対する評価等を継続的に検証する、会社法解釈等総点検研究会を設置する。 |
 |
| ◆ 上村達男教授 渡辺宏之准教授 |
| ■ 清水真人 熊潔 |

| III-c. フランス・EU企業法総合研究 |
欧州のなかでも、ローマ法および中世における先進商業国家であったイタリアの伝統を直接に引き継ぎ、 現在でも、いうまでもなくドイツとともにヨーロッパの中心を占めているフランス法を対象にすることで、 ローマ法以来の法の伝統を背景にしながら、今後のEUの展開という将来も見据えて、企業というものの法的な捉え方、 あるいは企業をめぐる法のあり方を、いわば多面的、立体的に検討する。
研究対象は、会社法、商取引法などの伝統的な商法の視点だけではなく、 競争法、資本市場法、銀行法または金融法をも含めた広い意味での企業法制全般とする。 また、企業法制の前提になる民法、および、法人のあり方を規定する憲法からの視点も検討の対象とする。
啓蒙思想と人権宣言、市民革命の地、フランスで企業社会と市民社会は思想的にどのような調和を保っているのか、 法令の形をとらない見えざる企業社会の規範意識は何か、企業社会でのフランス的こだわりは何を尊重するものなのか、 本COE企画の問題意識にとって有益な貢献をすることができると考えている。 |
 |
| ◆ 鳥山恭一教授 |
| ■ 内田千秋 |

| III-d. スカンジナビア諸国における企業と社会 |
| EU先進諸国の企業法制度の研究といえば、どうしても英米独仏を中心としたものになりがちである。 しかし、ノキアの例もあるように、ノルウエーやスウェーデンのような北欧諸国も世界的企業を抱える先進工業国であり、 またシェルやフィリップスなどを抱えるオランダ(近時、航空業界の統合の動きも報道された)を含むいわゆるベネルックス三国、 エストニアなどのバルト三国、そしてその北海・バルト海周辺国の接合部たる要衝に位置するデンマークなど、 いわゆる北ヨーロッパの企業社会と法制度に関する研究は、わが国ではかならずしも十分でなかったように思われる。 特に、スカンジナビア法制と呼ばれるスウェーデンなどの法制度は、 その「利益衡量法学」を支える文化ともども研究しなければならない法領域であると考えられる。 またドイツ法的でありながらアングロ・サクソン族の故地であったことを思い出させる法制度を有するオランダ、 そしてデンマーク法制(旧領土であるアイスランド法も含め)は、対岸のイギリス法との比較研究も可能であろうかと思われる。 EU法の一部ではあるが、独自の法領域として、北ヨーロッパに焦点を絞った研究グループを立ち上げ、 企業社会と市民社会がどのように共存しうるか、というCOE拠点の問題意識に迫る研究活動を行っている。 |
 |
| ◆ 尾崎安央教授 松沢伸准教授 |
| ■ 和田宗久 |
 ▲ページのTOPへ ▲ページのTOPへ
| IV-A. 企業と市場に係る刑事法制 |
| 企業と市場に関する法制の実効性を担保するための最も伝統的な手段は刑事罰である。伝統的な刑事法の発想は市民社会対応型と考えられ、その意義が低下す ることは決してない。しかし企業と市場に関する法制は、日々大規模に変化する市場と企業を対象とし、かつ複雑な利害が絡み、かつ先端的な金融手段は不正手 段をも先端的で補足しがたいものとするため、日々市場で生起する不正に確実に対するためには、様々な中間的な制裁手段や現場での制裁手段の活用が不可欠と なる。またこれら法制が守ろうとする保護法益も、日々変化する可能性もある(投資者保護から市場機能の確保等)。会計規範が刑事罰を伴うものであることは アメリカでは当然であるが、そうした認識も市場の成長とともに高まっていく。本企画は刑事法の研究者と企業・市場法制の研究者との共同研究を通じて、市場 犯罪の性格・保護法益、法人処罰の意義、法人処罰にまつわる時効の意義、中間的制裁手段等々について新たな研究上の展望を開き、具体的な制度論に生かそう とするものである。これまでに、内閣府の支援を得て企業不正等に関する日本初のアンケート調査を実施するなど、見るべき成果を上げている。 |
 |
| ◆ 田口守一教授 野村稔教授 曽根威彦教授 甲斐克則教授 |
| ■ 小野上真也 新谷一朗 |
 ▲ページのTOPへ ▲ページのTOPへ
| V-A. 変容する企業組織・労働市場と<労働世界>における法創造の課題 |
本研究拠点の目的に沿って、企業法制・資本市場法制とともに、労働法制もまた市民社会の質を規定するものであることを明らかにする。研究対象である企業 組織は、労働という角度からみると、労働組織としての企業組織、事業組織としての企業組織、会社組織としての企業組織という三つの側面において、その意義 と役割を分析することができる。
労働の角度から特に注目されるのは、第一に、一つの法人格内で完結しない企業組織(「グループ経営」)の出現が労働者に及ぼす影響であり、第二に、労働 組織としての企業組織の構成員の雇用形態・契約形態の多様化が急速に進行していることである。期間の定めのない雇用契約を締結し、終身雇用を享受できる正 社員が減少する一方でパート、派遣、臨時などの非正規社員が企業組織の構成員として重要な位置を占めるようになってきており、そうした組織構成員の変容 は、労働者派遣法や職業安定法の改正等によって促進されているが、ここでもこうした問題が労働者にどのような影響を及ぼすのかという観点からの法的解明は 遅れている。第三は、こうした企業組織と労働市場の変化が女性労働の変容とも関連していることである。労働市場の女性化といわれる事態は、様々な雇用形態 にある女性を企業組織の構成員として内部化しつつ、仕事と家庭の問題を新たな段階で顕在化させつつある。労働者はまさしく生身の市民そのものであるから、 こうした諸問題の解明は、企業社会ひいては市民社会のあり方を考える上で、絶対に避けることのできない問題である。企業法制との共同研究は成果を生みつつ ある。 |
 |
| ◆ 石田眞教授 島田陽一教授 |
| ■ 細川良 |
 ▲ページのTOPへ ▲ページのTOPへ
| VI-A. 次世代倒産法制のあり方の研究 |
| 世界的な経済産業の構造的な変化に伴い、企業倒産法制、すなわち危機企業に関するリストラクチャリング・ルールをより効率的かつ経済実態に即して制度設計し運用することは必須である。近年日本の倒産諸法は改正作業が一段落したところであるが、あらためて企業倒産法制における本質的問題、すなわち(1)企業の本質論、継続企業価値論の再評価、(2)企業倒産法の達成すべき目的、(3)あるべき企業倒産法制の制度設計についての研究を試みることが必要とされている。本研究企画では次世代倒産法制の提案を目指し、企業理論、ファイナンス論そして倒産法学の見地から複眼的視野に基づく学際的研究を行なうことを目 的とする。 |
 |
| ◆ 加藤哲夫教授 岩村充教授 上村達男教授 長野聡客員准教授 |
| ■ 杉本和士 |
 ▲ページのTOPへ ▲ページのTOPへ
| VII-A. 知的財産法制研究センター |
知的財産法制研究センターを設置する趣旨は、すべての企業にとって不可欠な最重要戦略部門として位置付けられている知的財産保護法制が、 西欧において、株式会社制度と同様の長い歴史を有しながら、近年に至って急速に重要性を高めている分野であることから、 これを本プログラムの問題意識と一体の、いわばマイクロコズム(縮図)と捉えることにより、サテライト的なものとして本センターを位置付け、 本拠点の問題意識と研究環境の下に位置づけることがもっとも適切と考えられたためである。 同センターは本プログラム全体の研究体制に組み込まれる形で理論研究を行っていくが、 さらに、あるべき知的財産法制を先駆的に確立していくことを目指し、 さらに知的財産紛争の予防・対応・処理のための紛争事例検索システムをアジアを中心に構築し、具体的な問題処理にも携わることを目指している。
本COE拠点の問題意識は、欧米型制度の現状と問題点を追求し、真に安定的な日本の企業法制を構築するという点にある。 そこで、知的財産法制研究センターでは、かかる問題意識に答えるため、現在主流の官僚主導型の政策立案から、 独立した民間の立場から政策提言を行いうる研究組織を形成し、 わが国の知的財産法制の適正な発展を企図するという思い入れから様々な企画を設定しようと考えている。 国家レベルの政策論議に真正面から参加するためには、単に官僚主導で立案された政策を検証するだけではなく、 十分な調査と研究に裏付けられたアカデミズムの立場から、 国家の政策決定において無視し得ない一定の政策提言(法システムの創造)を積極的に行っていくことが課題となる。 制度の基本構造に遡った歴史的・哲学的研究も、近時、法変動の著しい知的財産法の分野において、 時流に踊らされないアカデミズムの立場から知的財産制度を超然と論じていくための手段として必要となる。 |
 |
| ◆ 高林龍教授 木棚照一教授 |
| ■ 張 睿暎 小川明子 兪 風雷 五味飛鳥 崔 紹明 |
 ▲ページのTOPへ ▲ページのTOPへ
| VIII-A. 21世紀のコーポレート・ガバナンスと法システムの創造 |
| 21世紀における企業社会のあり方を考えるにあたっては、企業とそれをとりまく様々な構成員(株主、従業員、取引先、顧客、地域社会など) の行動とその関係(コーポレート・ガバナンス)を考察することが不可欠である。 そして、より有効なコーポレート・ガバナンスが実現されるためには、いかなる法が必要となるのかも検討されなければならない。 さらに、これらの考察を通じて日本の企業社会にとって必要な制度構築の視点を提示するために、各国の文化的、歴史的背景を十分に考慮した上で、 市民社会で企業が果たすべき役割は何か、そしてそれは国ごとにどう違うのかを探求することが必要となる。 その意味で、本研究の方法は、本拠点の1つの特徴「市民社会のあり方、その背景にある思想や歴史、哲学をも対象とする掘り下げた研究を行い、 それを踏まえてあるべき姿を探求する」にそったものである。 各国の文化、歴史、慣習を考慮に入れた、アメリカ型ではないコーポレート・ガバナンスのモデルを世界に向けて提唱する社会的意義はきわめて大きいと考えら れる。 |
 |
| ◆ 宮島英昭教授 |
| ■ 潘健民 |

| VIII-b. 20世紀日本企業の企業統治と企業行動・パフォーマンス |
本プロジェクトは、1900年から今日までの約1世紀にわたる日本企業における企業統治構造と、 企業行動、パフォーマンスの関係を実証的に分析し、 今後の望ましい企業法制・資本市場法制のあり方について経済学的なインプリケーションを提示することを目的とする。
望ましい制度設計を展望するためには、法制・資本市場法制が対象とする企業行動に関する実証的な分析の蓄積が不可欠である。日本企業の統治構造を歴史的 に概観すれば、戦前期の日本企業は、創業者が経営にあたる企業家型企業が高い比重を占め、また、経営執行を専門経営者に委託した企業でも、その所有構造や 株主の経営への関与は、株式が広範に分散し、 実質的権限を経営者に全面的に委譲する経営者企業から、封鎖的所有を特徴とし持株会社が強い実効的支配力を行使する企業まで、著しく多様であった。した がって、戦前期の日本企業は、今日と並んで統治構造が多様であり、その統治構造が企業行動・パフォーマンスに与えた影響を分析対象とすることによって、今 日の日本における望ましい企業統治のあり方に対して、一定のインプリケーションを与えることが可能になると考えられる。 |
 |
| ◆ 宮島英昭教授 花井俊介准教授 |
| ■ 今城徹 乗川聡 |

| VIII-c. 企業活動の変容に対応する会計・ディスクロージャー制度のあり方 |
会計・ディスクロージャー制度は、現代の企業法制の基本的インフラを提供する制度である。 企業活動が国際環境や情報技術環境などの変化に伴って大きく変容してきている今日、わが国の会計・ ディスクロージャー制度のあり方を大局的な視点から包括的に検討していく必要がある。本企画においては、 (1)企業法制における会計・ディスクロージャー制度の位置づけについて法律的・制度的なアプローチによって検討し、 (2)会計・ディスクロージャー制度の根幹にかかわる具体的な会計問題(資本制度、連結会計、業績報告、 概念フレームワークなど)について会計基準設定の観点から検討し、 さらに、(3)投資家等の情報利用者にとって有用な会計情報を提供するために望ましい会計・ ディスクロージャー制度や会計基準の方向性について規範的・実証的な視点から検討していく。
また、企業活動の国際化に伴って、会計基準の国際的調和化(ないし統一化)の作業が進められており、 この問題についても、わが国としての対応のあり方を模索し、国際会計基準委員会、 米国財務会計基準審議会などの主要基準設定機関の他、EU諸国・アジア関係諸国との連繋を深め、 相互交流や共同声明などの具体的な成果に結びつけていく。 |
 |
| ◆ 鳥羽至英教授 川村義則准教授 |
| ■ 潘健民 菅野浩勢 ジュロフ・ベチェスラフ |
 ▲ページのTOPへ ▲ページのTOPへ |
|
|